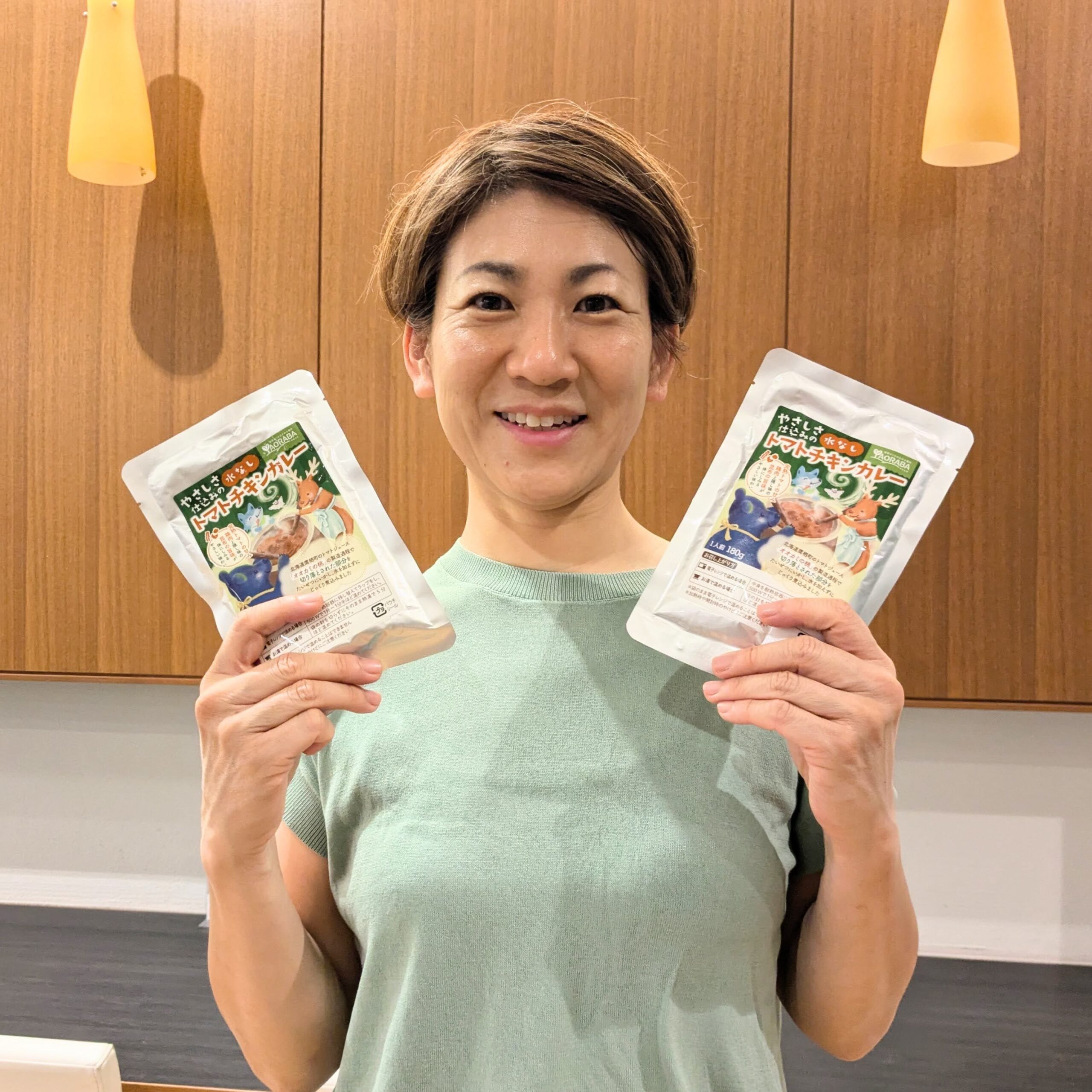外食時の食べ残しを持ち帰る「mottECOモッテコ」の取り組みが社会に浸透しつつあります。そんな中、7月1日に開催された「mottECOフェスタ2025」で実現した農林水産省の鈴木学氏と株式会社セブン&アイ・フードシステムズの中上冨之氏による対談と、環境省の村井辰太朗氏へのインタビューを、CE.Tにて独占収録させていただきました。
「食品ロスというニッチなテーマにもかかわらず、昨年を上回る多くの来場者があり、社会情勢が変化してきたことを感じます」と中上氏が語るように、着実に広がりを見せる食品ロス削減の最前線から、その成果と課題を探ります。
広がりをみせるmottECO、官民一体の食品ロス削減

mottECO普及コンソーシアムの設立者で代表を務める株式会社セブン&アイ・フードシステムズの中上冨之氏(写真左)
— mottECOフェスタ2025、大盛況です。主催者として、講演者として、お二人はどのような感想をお持ちですか。
鈴木氏:まずは中上さん、今日は本当におめでとうございます。大盛況ですね。僕は昨年も出たんですが、やはり昨年よりもさらに大盛況だと思います。いろいろな方々が入ってきているということで、すごくいいと思います。講演者として、というよりこういう機会に我々も参画する機会をいただきまして、本当にありがとうございます。
中上氏:おっしゃっていただいた通り、1年目、2年目に増して来場者も多いですし、出店ブースも過去最大なんですね。なので年々こう世の中の空気感というか食品ロスというある程度ニッチな狭いテーマにもかかわらずこれだけのご来場者がいるというのは、社会情勢が少し変化してきたかなというのを肌身で感じています。
— パネルディスカッションの冒頭では、小泉大臣のビデオメッセージがありました。これはコンソーシアムとしては心強い応援なのではないでしょうか。
中上氏:本当に心強くてですね、我々はもちろん実践事業者として仲間を増やしていくということについては頑張っていますけれど、やはり参加に対してまだまだ不安に思っている事業者や自治体には、小泉大臣のメッセージというのは非常に大きな影響になるという風に感じており、感謝しています。
鈴木氏:小泉大臣のメッセージに、私も、今日一緒にやってくれたスタッフも心動きました。本当に嬉しくて元気が出て、さらに新しいことができるんじゃないかと思っています。

食品ロス削減率58%達成の裏側 - 外食産業の課題とは
— 先日公表された統計では、事業系食品ロスの目標であった2000年度比半減を大きく超えて、2023年度で58%削減されたと発表がありました。この成果をどう受け止めていらっしゃいますか?
鈴木氏:これから60%を削減という目標にするにあたって、いろいろな議論がありました。特に食品事業者の皆様のご意見をいただきながら、しっかり議論してきたと思っています。先日発表された2023年度の実績も、58%達成ということで、これも行政だけでなく食品事業者さんの取り組みがまずあってのことと思っています。
加えて一番重要なのが、消費者の皆様がどういう風にこれを捉えていただけるか、一緒にやっていただけるかということだと思います。そういう意味では、みんなで一緒にやっていくということを、これからもやっていきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。
中上氏:60%の目標に近づいているから良し、ではなく、講演の資料でも公開があったかもしれませんが外食事業者単体で行くと、一昨年のデータからは少し増えているというのが現実です。当然、コロナ禍の影響などは我々も織り込んではいますが、だからと言って食品ロスが出ていいというものではないので、ここについてはもっと自助努力は続けていきたいと思っています。
同業他社連携の苦労と成果
— mottECOはコンソーシアムという形で、多くの同業他社や、4つの省庁が関わる取り組みになっていますが、ここまで来るまでに大変だったことはありますか。
中上氏:とっても苦労がありました。順調に仲間が増えているように見えていると思いますが、実際のところは参加を一緒にしませんかとお声掛けしても、まだ時期が早いのではないかとか、食品安全上の不安や懸念が払拭できないという事業者や自治体もいらっしゃるので、それはもちろん仕方がないというか、ある程度あって当然だと思っています。
我々は粛々としっかり実績を積み上げながら、コンソーシアム全体で今年、年間30万件のmottECOの利用がある中で、事故も苦情も起きていない、こういった実績をしっかり積み上げていって、世の中の当たり前にしていく。世の中の当たり前になれば、今不安がっている事業者や自治体も参加しやすくなるというところを、世の中の情勢づくりを一生懸命やっているところです。
3つの視点で生み出す新たな可能性
— mottECOのような民間発の仕組みの存在は、どのように映っていますか。また、こうした枠組みに対する期待をお聞かせください。
鈴木氏:すごく心強いということが、私がまさに感じていることです。単に力強いだけじゃなく、いろいろな方々が入ってきていただいて、それぞれ抱えている懸念などもシェアして、うまくいった事例もシェアする。中上さんがパネルディスカッションでおっしゃっていたように、同業他社でも実は協働してやっているという、ここがすごくパワーの源かなと思っていまして、ありがたいなと、我々も一緒にやっていきたいと思います。
大きく3つの視点があると思っています。1つは新しいイノベーションですね。社会的な動き、それから技術をうまく取り入れていくことで前に進めるんじゃないかと思っています。それから2つ目はやっぱり連携、パートナーシップがすごく重要だと思っていまして、このmottECOのイベントに出て、さらにそれを感じたんですが、いろいろな方が来て考えていることをシェアしていくことで、新しいことができるんじゃないかと。これから新しいどんなものが、このコンソーシアムで出てくるのか、期待しています。
3つ目は、楽しくしていくっていうことですね。こうした取り組みが新しいものを作り出すと僕は信じていますし、もっと広がっていくと思っていますので、楽しく、ワクワクすることをやっていけるといいのかなと思っています。
中上氏:先ほどのディスカションでも最後に言わせていただきましたが、この取り組みは食べ残し持ち帰りを推奨していこうという一義的にそうしようという取り組みではなくて、そもそも我々は飲食事業なので、せっかく心を込めて作ったものは全部召し上がっていただきたいというのが本音ですから、食べ切りが第一義的な発信です。
それでもなかなかゼロにならない食べ残しを、今まではごみとして捨てていたものを、捨てないでしっかり食べ切るという取り組みなので、将来的には皆さんが自分が頼んだものは全部食べ切るんだっていう、もったいないの精神が、もう1回日本人が思い出していただければ、この拡大はどこかで止まっちゃってもいいのかなという風に逆に思っています。
「今日からできる、明日からできる取り組み」
— 連携ということについて、すごく重要だとおっしゃっていますが、どのように色々な事業者や自治体、省庁と連携していきますか?
中上氏:外食事業者なので外食のチェーン店に声掛けは地道に続けていきますが、一般消費者の方が普段使っている食堂で持ち帰りが当たり前にできる環境を作っていくためには、個人店の参加が一番重要だと思っていますので、そういったところへのアプローチをぜひ自治体の力をお借りしながら、あとは国のバックアップをいただきながら進めていきたいという風に考えています。
— mottECOを導入したいと思っている事業者さん、あるいは自治体へ向けてメッセージをお願いいたします。
中上氏:mottECOは事業者にも、お客様にも、社会にも、基本的には損のない取り組みだと思っています。なので、ぜひ試しにでもいいので一緒にやってみていただいて、一歩踏み出してみればそんなに難しいことじゃないなっていうのが分かると思いますので、今日からできる、明日からできる取り組みとしてぜひご参加をお願いいたします。
鈴木氏:このデザインがまずいいですよね、これ一緒にやってみようという感じになります。重要なのがまず食べ切るっていうことが大切で、本当にしっかりと伝えていくことが大切だと思います。どうしても残ってしまった時にはmottECOを思い出す、本当にそれが重要かなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。
消費者の行動変容を促す転換点に
続いて、パネルディスカッションにも登壇された環境省の村井辰太朗氏へ独占インタビューをさせていただきました。

—本日のmottECOフェスタをご覧になって、どのような印象をお持ちですか?
村井氏:私はmottECOフェスタに参加するのが今回で2回目なのですが、昨年以上にいろんな方が参加されて盛り上がりを見せていて、本当に素晴らしいことだなと思います。
—パネルディスカッションでの客席の反応はいかがでしたか?
村井氏:はい、ありがたいことにほぼ満席で、熱意を持って参加いただいたと感じています。終わった後も色々なご質問をいただいたり、実は興味あるんですよという話もいただいているので、まだまだ広がるポテンシャルがあるのかなと感じました。
—mottECOは環境省の補助事業としても認定されていますが、このような官民連携の制度づくりを、環境省としてどう位置づけていますか?
村井氏:食品ロスは、温暖化の問題と同様に、どこか特定の誰かが出しているというよりは、みんなが関わっているものだと思います。そのためには、多様な主体の皆様のご協力が必要という意味で、やはり行政だけでは限界があり、官民連携というのが重要ですので、そういった意味でもこのイベントは大変重要な位置付けと考えています。
また、先ほどの小泉大臣のメッセージもありましたが、小泉大臣が環境大臣になった時にスタートした事業ですので、mottECOを通じて食品ロス削減について意識をしていただければ、家庭での食品ロス削減にもつながるといった副次的な効果もあると考えています。そうした意味でもここで色々な普及啓発や、連携をすることが非常に重要かと考えています。
—事業者による「持ち帰り」推進は、これまで衛生リスクなどが障壁となっていました。そうした行動変容を促すmottECOのようような制度に、どのような意義を感じておられますか?
村井氏:まず、食を通した安心安全というのは当然重要だと思っていますし、環境省としてもやはり人の健康を守るというのは重要なミッションですので、そこは最低限守らなければならないと考えています。同時に、いろいろな食品ロスも問題があるからこそ、持ち帰りというのも重要だということで、厚生労働省、消費者庁と連携しながガイドラインを定めて、考え方を変えてやっていこうという、まさに転換点になっていると思います。
—食品ロスに関しては農水省、厚労省などとも連携されています。特に省庁間連携で重視している点や、今後の方向性があれば教えてください。
村井氏:各省庁はミッションを持っていると思います。それぞれ異なるからこそ、様々な切り口で食品ロスに向き合うことができると思っています。消費者庁は消費者行政で、環境省は環境面、農水省は食の面という形で、その輪が広がっているという状況にあると思います。そのような形で多様性を、多様な面でやるということを重要視していきたいと思います。
若い世代へのアプローチが未来を変える
—mottECOのような仕組みが広がっていくために、自治体や他業種への波及もカギになるかと思います。環境省として今後期待している分野やターゲット層はありますか?
村井氏:パネルディスカッションでもご一緒させていただきましたが、自治体の皆様の取り組みは今後ますます重要になってくるかと思います。自治体の皆様を通じて、消費者の行動変容を促すことが大事なんですが、特に若い世代、今日も学生の方々が参加されていますが、若い世代の行動が変わると多分その未来に渡って行動が変わっていくということですので、若い世代へのアプローチというのも大切にしていきたいと思っています。
—最後に、生活者や事業者へ向けた、食品ロス削減のアクションについて環境省からのメッセージをお願いします。
村井氏:食というのは皆さん、生活に切っても切れない重要な要素でありますので、その中で食品ロスが出るというのは、やっぱりもったいないというのは皆さんも感じていることだと思います。いろいろやることはあるのですが、無理をせず、けれどちょっとずつやっていくことが、未来につながって環境の面にもいいことになりますので、ぜひ一緒に協力してやっていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
—ありがとうございました。