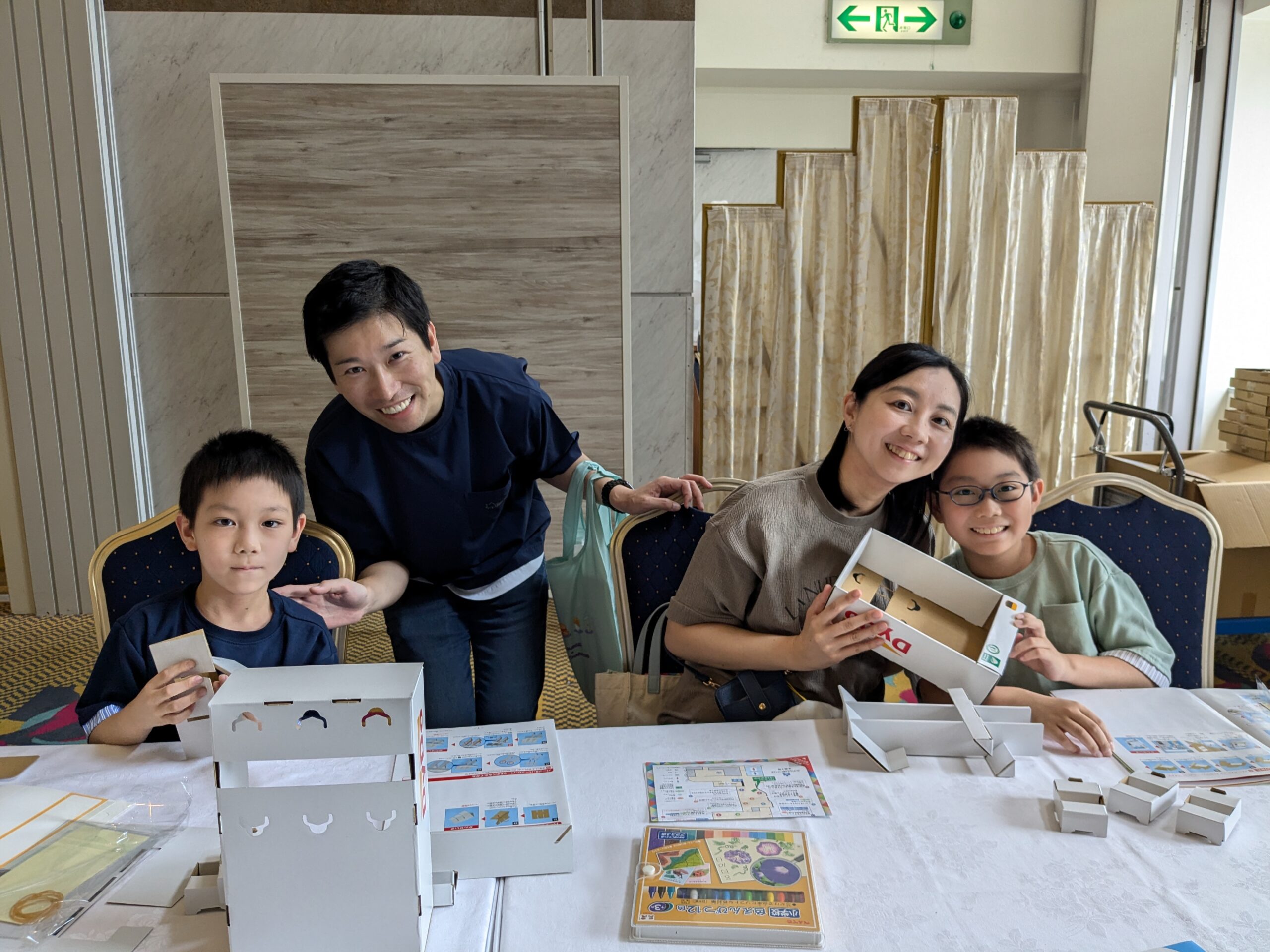駐車場1台分に収まる、都市型リサイクル機器の実力
2025年6月上旬、香港を訪れ、食品リサイクル事業を展開するAEL社の現場を視察させていただきました。現地では、コンパクトに設計された発酵処理機械が稼働しており、都市部の限られた空間でどのように食品廃棄物を処理しているかが紹介していただきました。

視察したモデルは、200kg程度の処理能力を持ちながらも非常に省スペース設計で、わずか駐車場半分のスペースに収まります。投入した食品廃棄物を破砕し、水と混合することでスラリー(汚泥)状に加工し、できたスラリーはタンクに貯蔵され、一定程度たまるとタンクローリー車で回収されます。
これまでは毎日、収集車が袋入りの廃棄物を回収しましたが、この設備を入れることで週に一回の回収で済むようになったとのことです。人件費や燃料費の高騰、また香港の道路事情の悪さを考慮すると、十分に費用対効果の合う投資です。
また、都市型ということで臭気対策がしっかりなされており、投入時以外はほとんど気になりません。オゾン脱臭装置に加えて、タンクからのスラリー積込時もホースを用いて外気に触れない構造になっています。
また、香港では国営の大型メタン発酵施設である現在、O·PARK1(容量日量200トン)が稼働中で、生ごみを堆肥やバイオガスにリサイクルしています。政府は2020年代半ばに第2施設O·PARK2を稼働させる計画で、生ごみの分別収集ネットワークも拡充しています。この設備で作られたスラリーもO·PARK1に搬入されています。
AEL社の事業は、この香港の国策に沿ったものであると言えます。AELの担当者はさらに、「都市部の土地制約を考慮した処理機の設計が不可欠」と述べ、処理効率とスペース効率を両立させるために試行錯誤を重ねてきたと説明してくれました。現場では、スマートフォンによる遠隔制御にも対応しており、保守や稼働管理の省人化にも配慮された設計になっています。
香港の課題と対応策 ― リサイクル文化の定着に必要なこと
現地での対話では、日本と香港における廃棄物処理文化の違いについても話が盛り上がりました。AELの担当者は、日本の細かい分別や市民の高い意識を「特殊で成熟した文化」と評価しつつも、香港では同様の運用は現実的でないと語ってくれました。
「香港では、たとえ4分類であっても十分な品質管理が難しい。そもそも市民の意識が追いついておらず、政府もそのモニタリングにコストをかける余裕がない。」

このため、香港では分別数を増やすよりも、処理後のプロセス効率を高める技術の導入が重視されています。たとえば、発酵処理後の残渣をタンパク質飼料として再利用する方法では、中国・珠海での実証実験も進んでおり、養豚用飼料としての実用性が確認されているといいます。
また、教育制度にも課題があると指摘し、香港では小学校から試験重視の学習が優先され、公共意識や環境教育が後回しになっている現状を述べていただきました。これがリサイクル行動の根付きに影響しているとのことです。

再資源化ビジネスの収益性と、事業継続の実務的視点
事業としての再資源化が持つ現実的な側面について、香港の廃棄物処理ビジネスは大きな利益が出る分野ではないとのことです。特に堆肥化事業については、処理後の熟成・保管にかかる時間とスペースが大きな負担であり、さらに市場での価格競争力にも課題があるため、現地の堆肥は輸入品に比べて4〜5倍の価格になることもあり、販売は容易ではないそうです。
また、政府による支援や処理コストの補助制度も日本と比べると不十分であり、民間主導での工夫が求められております。
今回の訪問では、香港の都市事情に即した廃棄物処理技術と、日本とは異なる文化・制度環境の中での課題対応が紹介されました。
分別文化に依存しないリサイクルの進め方や、エネルギー・飼料など多用途な再利用設計は、今後の都市型循環モデルを考える上で示唆に富む事例となっております。

Jude氏へのインタビュー記事はこちらから