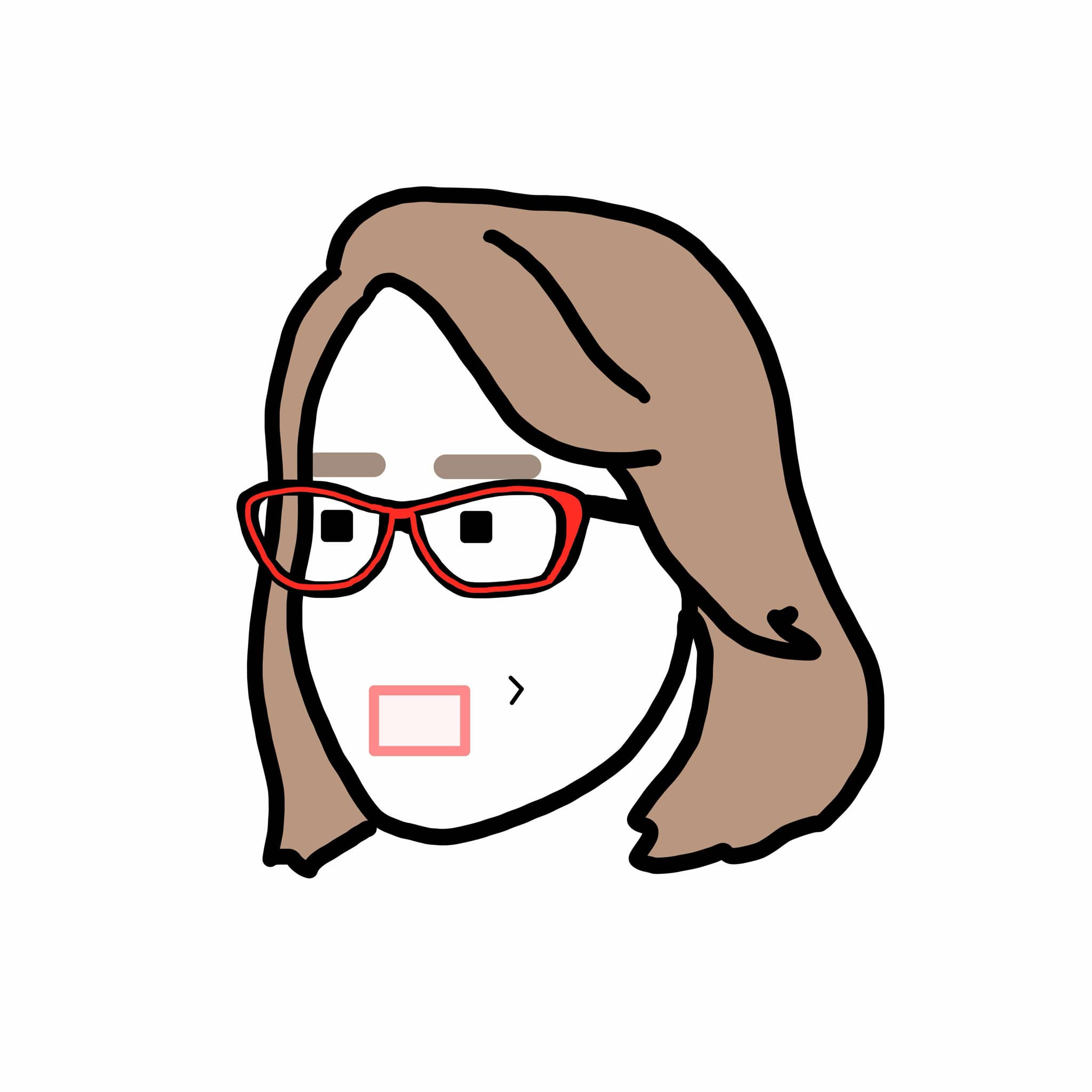ドイツ・フライブルグレポート第二弾は、自分たちで使用するガスや電気を、再エネで自前で作って、地域消費をまかなうだけでなく収益も上げている村をご紹介します。
「エネルギー自治」という考え方
「エネルギー自治=自分たちでエネルギーをまかなう」という発想は、多くの日本人にとってなじみがないかもしれません。屋根にソーラーパネルを設置して個人レベルで省エネをする人はたくさんいますが、町村単位でエネルギーを自前でまかなうという地域はごく一部。筆者自身も含めてほとんどの人にとって、エネルギーは電力やガス会社と契約して使用量を支払うもので、他に選択肢を考えないのではないでしょうか。
しかしドイツは環境大国と呼ばれるだけあって、電力会社に頼らず、地域単位で再生可能エネルギーを運営して「エネルギー自治」を実現している村がたくさんあります。シュヴァルツヴァルト(黒い森)の一角にあるバーデン=ヴュルテンベルク州のフライアムト村もそのひとつです。
酪農危機から再エネビジネスへ〜ある農家の決断
フライアムト村は、フライブルクの北東約20キロにあり、敷地は広範囲に広がりますが、人口はおよそ4000人ほどの小さな村です。ここでは太陽光、太陽熱、バイオガス、木質バイオマス、風力など、村人たちが自らの手で築いた分散型再生可能エネルギーの仕組みが回っています。
かつて酪農を行っていたラインボルト家では、牛や豚を育てつつ、トウモロコシを飼料用に生産していました。
ところが90年代末、BSE(狂牛病)の問題が起きます。その影響で酪農経営が困難になったことで再エネに活路を見いだし、大きな決断を行います。家畜をすべて売り払い、そのお金を投じて敷地内にバイオマス発電施設を建設するのです。

原料は自家生産のトウモロコシと、近隣から運ばれる家畜糞尿。それらをタンクにためてメタン発酵させ、できたメタンガスを発電する仕組みです。また、この農家は山林も保有しているので、発酵が弱い時には木質バイオマスで補完するそうです。持てる資源をエネルギー化のためにフル活用しているのです。
電力生産量は年間100万kWh(およそ200世帯が1年間に使用する量)で、自家と近隣で消費するほか、余剰は地域の電力会社に売電して収益を上げています。
かつては家畜用に生産していたトウモロコシですが、今はバイオガスの原料として生産を続けています。もちろん、メタン発酵時に発生する消化液は肥料として畑や牧草地で利用しており、エネルギー生産を主軸とした循環型農業が実現しています。
ラインボルト家のエネルギー活用はそれだけに留まりません。一般的には放熱してしまうことの多い発電時の排熱も熱源として販売しようと考えたのです。
そこで、まずは近くの小学校にかけあって暖房エネルギー提供の長期契約を取り付け、2000万円もの自費を投じ、熱供給のパイプラインを敷設するのです。小学校が成功すると、次はかなり離れた公共の温水プールにも同様にパイプラインを敷いて熱供給をしています。発電も発熱も、投資金額はおよそ13年から15年で回収できるとのこと。


いち農家がエネルギーインフラであるパイプラインを敷き、自分たちで生産したエネルギーを、地域の必要なところに供給する。その発想と、リスクの取り方に驚くとともに、個人レベルでそんなことまでできるのか、と考えさせられました。
市民の力で建てた風車〜共同出資で回る風力発電
フライアムト村では風力発電も行っています。ラインボルト家のエリアから山をずっと上がっていくと大きなタービンが現れます。


酪農を行うシュナイダー家の標高700メートルの牧草地では、農家を中心とした市民たちが共同で出資して建てた風力発電タービンがあります。
タービンは2基ありますが、訪れた時にはひとつは建て替え中でした。2基合わせて年間570万キロワット、約1900世帯分の年間消費電力に相当する発電を行っています。
この2基は、フライアムト村の村民と、周辺地域の市民合わせて142人が共同で3分の1を出資し、残り3分の2は銀行からの融資で建設しました。投資した市民には、売電量に応じて配当がもらえるしくみになっており、6%で回っているとのこと。風車は地域住民に利益をもたらす「共有財産」になっているのです。
「エネルギー自治」を成り立たせるもの
筆者は、故郷である福島の原発事故後にUターンし、風評払拭を軸とした地域活性の仕事に10年以上携わってきました。現在はサーキュラーエコノミーをテーマにした当メディアの責任者であり、研究者でもあります。そんな背景から、「地域の資源・エネルギー循環」の重要性を常に感じており、ライフテーマのひとつでもありました。
そんな中、エネルギー自治を行っているフライブルグのことを知り、いつか訪れたいと思っていたところ今回運良くそれが実現しました。
地域内で生み出されたエネルギーが、地域内で消費され、利益まで生み出し、それが再び地域に還元される。理想的と思える「エネルギー自治」の現場を見ることができました。
その成功の背景には、FIT(固定価格買取制度)の活用、地域の協同組合や地域エネルギー会社との連携などがありますが、それらはあくまで「手段」であり、それ以前のものがここに潜んでいると、案内をしてくれた池田氏の話を聞きながら感じていたのです。
帰国して、池田氏の著書(共著)『欧州のエネルギー自立地域』(学芸出版社)を読み返してみると、フライブルグの歴史的なことが書かれていました。
フライアムトの「フライ」は「自由」という意味を持つ。名前の起源は中世時代の村の「自由な農民」である。欧州の中世時代は、荘園制度のもと、農民は、領主に与えられた土地を耕し、領主に年貢を納めていた「農奴」であったが、フライアムト村では、各農家に比較的大きな土地とその相続権が与えられ、しかも領主に年貢を納めなくてもいい、という例外的な制度が取り入れられた。フライアムト村の農民は自由だった。この気風は現在も受け継がれており、フライアムトでは、他への依存を嫌う独立心旺盛な人々が多い。その村民たちが、自分たちの生活に必要なエネルギーは、化石燃料や原子力に頼らないで、自分たちで生産しようと立ち上がった。
引用:『欧州のエネルギー自立地域』(学芸出版社)③フライアムト村〜エネルギー事業が農家を支え、村を動かす
つまり、ここでは歴史的に農家の人々は「農奴」のマインドではなく、その真逆とも言える独立心が醸成されていました。それが私費を投じてエネルギー施設やパイプラインまで建設する、という自立心あふれる行動につながったのです。
エネルギーインフラには、お金だけでなく技術的なこと、法的なことも求められます。難題が続いたはずですが、それを乗り越えられたのは「誰か(強いもの)のいいなりになりたくない」「生活の根幹であるエネルギーで、人にコントロールされたくない」「生活に大事なことは自分たちで握っていたい」という強い想いなのでしょう。それは彼らの譲れない「生き方」、もっと言えば「尊厳」であり、それを守るためにはどんな労力もリスクも厭わない。それは、反原発から始まったヴォーバーン地区の自治にも感じたことでした。
平たく言ってしまえば、エネルギー自治には、やる側に相当な覚悟と「根性」が要ります。それも「ど根性」です。フライアムトは成功例として参考にはなるけれど、これを日本に、と思ったときに、やる側の準備が整わなければ安易に真似することはできないと感じます。
でも、だからといってあきらめるには早いでしょう。資源小国の日本において、エネルギー自立の考え方はこれから必ず求められます。そのために、自分でもできる道があるのではないか。その可能性を探ってみよう。フライアムト村訪問は、そう思える体験でした。