「第4回サーキュラー・エコノミーEXPO」が2025年2月19日(水)~21日(金)東京ビッグサイトにて開催されました。(主催:RX Japan株式会社)
同時開催の第23回スマートエネルギーWEEK【春】、第6回GX経営WEEK【春】を合わせて約1,600社、40の国と地域から出展があり、エネルギー政策など注目のセミナーも多数開催。3日間で69,308名が来場しました。
その中から、初日に行われた基調・特別講演「官民の連携によるサーキュラーエコノミーの推進」の内容をお届けいたします。近年、資源の有効活用や環境負荷低減を目指す「サーキュラーエコノミー」への注目が高まっています。この潮流の中で、政府と民間企業はどのような取り組みを進めているのでしょうか。

パネリスト
・経済産業省GXグループ 資源循環経済課長 田中 将吾氏
・トヨタ自動車株式会社 Chief Sustainability Officer 大塚 友美氏
・デロイト トーマツ合同会社デロイト トーマツ グループ執行役デロイト トーマツ インスティテュート代表 松江 英夫氏(進行)
資源循環政策の3つの柱と官民連携の重要性

(田中氏の講演より)
経済産業省では、サーキュラーエコノミーの推進に向けて3つの大きな柱を立てています。1つ目は「資源循環の促進」です。日本は資源小国であり、天然資源への依存度が高い状況です。一方で、国内には天然資源に匹敵する量の「都市鉱山」が存在します。これらを有効活用することで、資源調達リスクを最小化することが求められます。
2つ目は「環境制約への対応」です。従来の3R政策に加え、リサイクル技術の高度化だけでなく、ものづくりの在り方自体も問われています。欧州に目を向けると、エコデザイン規制のもとに実行させようとする動きが活発化しており、日本が培ってきた環境配慮設計を高い水準で、なおかつグローバルスタンダードにしていくことが大事です。脱炭素化の実現に向けても資源循環が重要な役割を果たし、再生資源の利用や製品の長期使用によってCO2排出が不可欠となっていきます。
3つ目は「経済成長の機会創出」です。サーキュラーエコノミーはビジネスチャンスでもあります。資源制約やカーボンニュートラルの要請に対応しつつ、それを成長につなげていく取り組みを進めています。
産官学で目線を合わせた連携が不可欠
これらの目標を実現するためには、産官学で目線を合わせた連携が不可欠です。そこで私たちは「サーキュラーパートナーズ」という枠組みを立ち上げ、625社もの企業や自治体に参加いただいています。ここでは2030年、2040年に向けたビジョンとロードマップの策定を進めており、業界ごとの具体的な行動計画も検討しています。「産官学連携」「投資支援」「ルール整備」の3点セットで取り組んでいるところです。
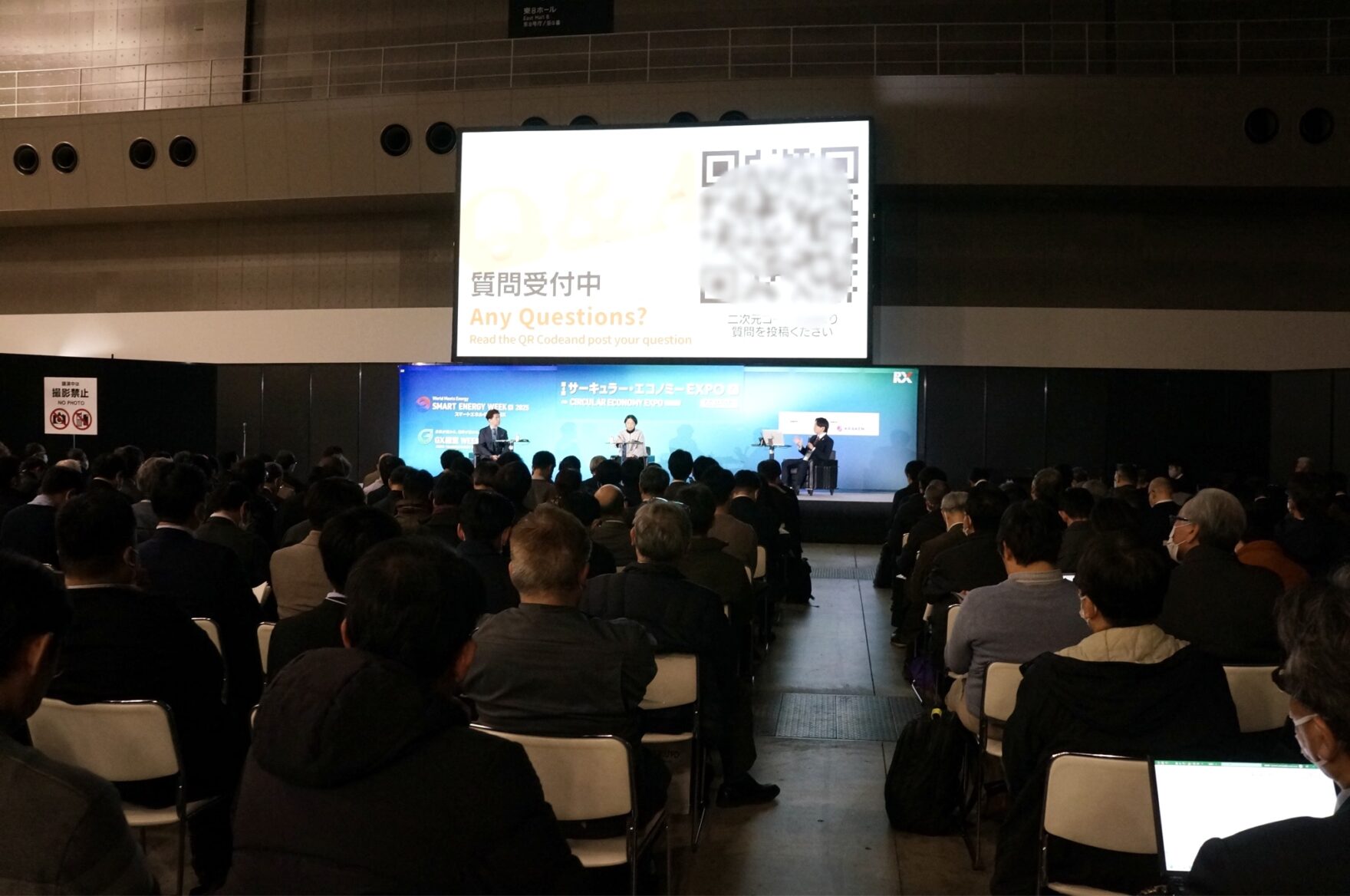
法制度の整備と国際標準化への挑戦
具体的な政策としては、世界標準を獲得していくための投資促進について、単年ではなく3年間使っていただける予算を経産省として100億円、環境省でも200億円、合計300億円を措置しており、額も引き上げていくことが可能な状況です。
さらに現在、資源有効利用促進法の改正も進めています。主に4つの柱があり、1つ目は再生材利用の拡大です。戦略的な素材を政令で指定し、その素材を大量に使用する企業に再生材利用計画の策定と報告を義務付けるものです。2つ目は環境配慮設計の促進です。製品設計の段階から再生材利用を考慮するよう、環境配慮設計を認定するトップランナー制度の導入、資源自律経済実現に向けた取り組みが行われています。
3つ目は自主回収の促進です。資源性の高い製品について、廃棄物処理法の規制を緩和し、メーカーによる回収を容易にします。4つ目はリユース・リペア市場の健全な発展を支援する制度の整備です。
また、国際的な動向にも注目しています。例えば欧州では、自動車のバッテリーや車体に使用されるプラスチックについて、再生材の使用を義務付ける規制が導入されつつあります。こうした動きは世界中のブランドオーナーに影響を与えており、日本企業も無関係ではいられません。そのため、国内でも循環資源のマーケットとサプライチェーンの構築が急務となっています。
「トヨタ生産方式」で考えるサーキュラーエコノミーの未来像

(大塚氏の講演より)
トヨタ自動車では、1970年代から資源循環に取り組んできました。2015年には「環境チャレンジ2050」を策定し、脱炭素と並んで資源循環型社会システムの構築を目指すことを宣言しています。車はとても長いライフサイクルを持っていますので、様々なステージのステークホルダーの皆様と技術開発や仲間づくりを行なっています。
私たちが大切にしているのは、トヨタ生産方式の考え方です。無駄を省くという精神、文化を基盤にサーキュラーエコノミーへの取り組みを進め、「社会と企業のサスティナビリティを同期化する」ことを目指しています。具体的には「技術開発」「パートナーシップの構築」「ビジネスモデルのシフト」という3つの観点から施策を展開しています。
例えば、2003年から解体分別しやすい「易解体設計」を新型車に採用しています。例えばワイヤーハーネスという電線の束を、どこを通しておくと解体時に邪魔にならないのか、少ない力で解体できるよう静脈産業の皆様からもフィードバックをいただいて設計することで、リサイクル率の向上につながります。現在、設計数値上のリサイクル可能率は85%以上となっています。また、現場初の試みとして、自分たちで解体してみる取り組みも行い、そこで得られた知見を設計に生かしています。
他にも、ペットボトルを社内で分別・回収して、ランクルのシートに再生したり、環境に携わるメンバーや設計者だけでなく全社員でサーキュラーエコノミーの意識を高めています。
再生材の採用も積極的に進めており、2030年までに再生材の採用率を30%以上にすることを目指しています。バンパーだけでなく、内装材など目に見える部分にも再生材を使用する技術開発を行っています。さらに、トヨタが培った電池の技術を活かした「蓄電池」のシステム構築も、脱炭素の面から重要視しています。
ビジネスモデルの変革とグローバル展開の課題

私たちは、カーメーカーから「モビリティカンパニー」への転換を目指しており、単に自動車を製造・販売するだけでなく、移動という体験そのものを提供するビジネスモデルへの変革を進めています。
具体的には、アップデート可能な設計の導入、例えばソフトウェアだけでなく、ハード面からもシートの表皮や安全装備などを後から最新のものに交換できるような設計を考えています。これにより、従来は車を販売した後の顧客接点が少なかったのですが、売り切りではなくお客様とのタッチポイントが増え、ビジネスの成長機会にもつながると考えています。
また、欧州の例ですとイギリスでは中古車のリファービッシュ、中古整備品パーツのビジネス化など、新車を造るだけはでない工場の機能を拡張する取り組みも始めています。
エコシステムの重要性において、デジタルのトレーサビリティも大事ですが、フィジカルに静脈の部分で循環されるシステムも不可欠です。海外での資源循環の取り組みには確かに課題があり、各地域で適切な処理やリサイクルの仕組みが整っていないケースもあります。そこで私たちは、日本で培った技術やノウハウを活かし、各国でのキャパシティビルディングや適切な処理施設の整備支援などを行っています。
特に規制のない地域では、適切な回収や処理の仕組みづくりが重要です。そのためには、現地の実情に合わせたルール作りも必要になってくると考えています。
官民、業界を超えた連携やルール整備、生活者の方々と一緒に学び、会話しながら取り組んでいく議論が巻き起こっていくことが大切だと思います。
官民連携で経済性と国際競争力を強化
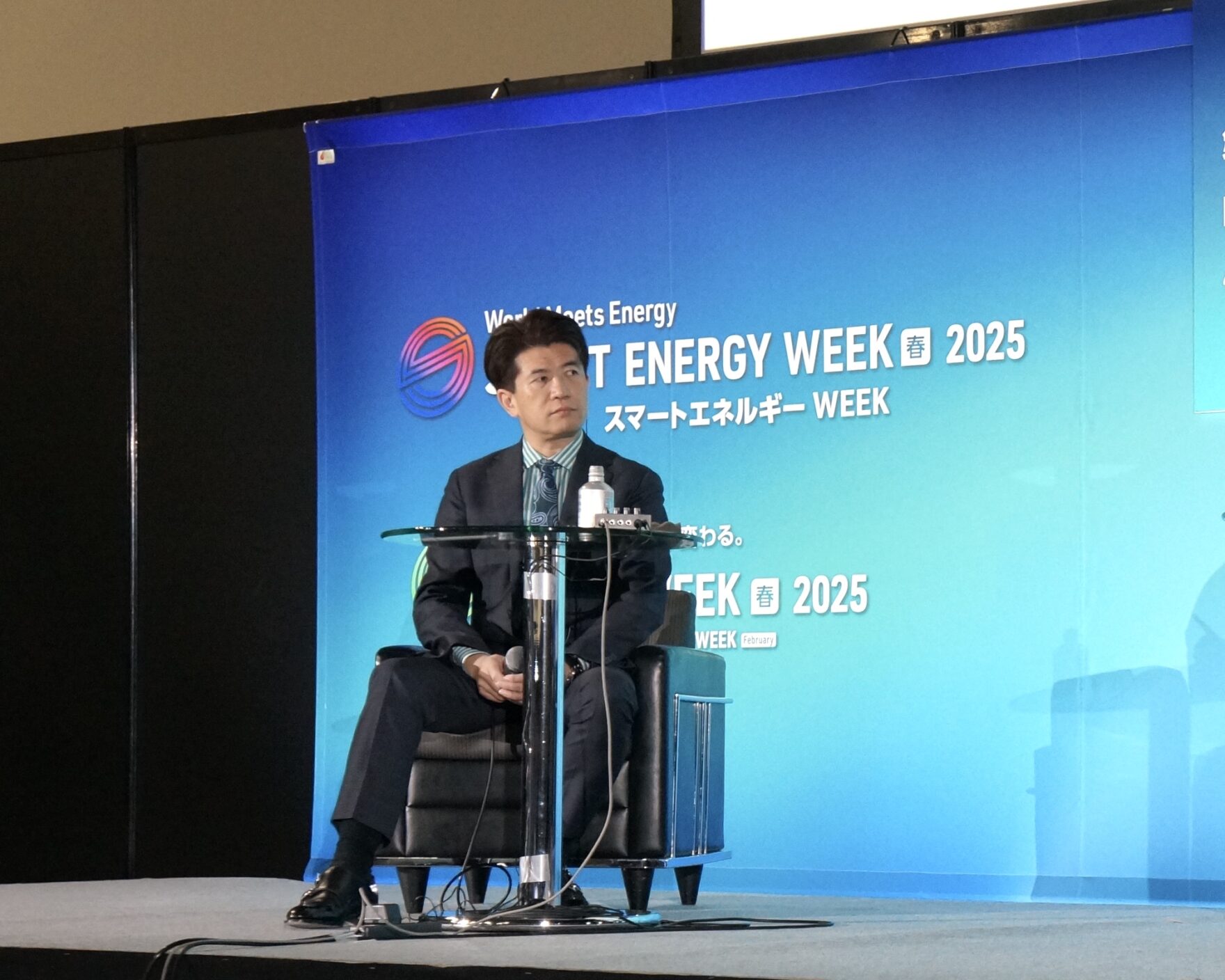
講演後半には、官民連携による経済合理性の追求と国際競争力を強化するためのディスカッションが行われました。サーキュラーエコノミーに対する課題意識の高まりにより「価値循環」が起きており、水平的成長から時間軸の成長への転換が求められています。
垂直統合的な戦略の重要性、パートナーを作り、社会全体の経済合理性と企業の経済合理性を近づけながら、グローバルな規制動向とも調和させる必要があります。トヨタ自動車が取り組む製品の長期利用やアップデート可能な設計は、一見コストがかかるように見えますが、お客様との関係性を強化し、ライフタイムバリューを高めることができます。
日本の強みである現場力とチームワークを活かし、グローバルでも通用する実行可能なアプローチを示していくこと。社会的インパクトとビジネスチャンスを両立させ、官民が連携しながら、セクターを超えて社会全体でサーキュラーエコノミーを推進していく重要性が改めて示された講演でした。






