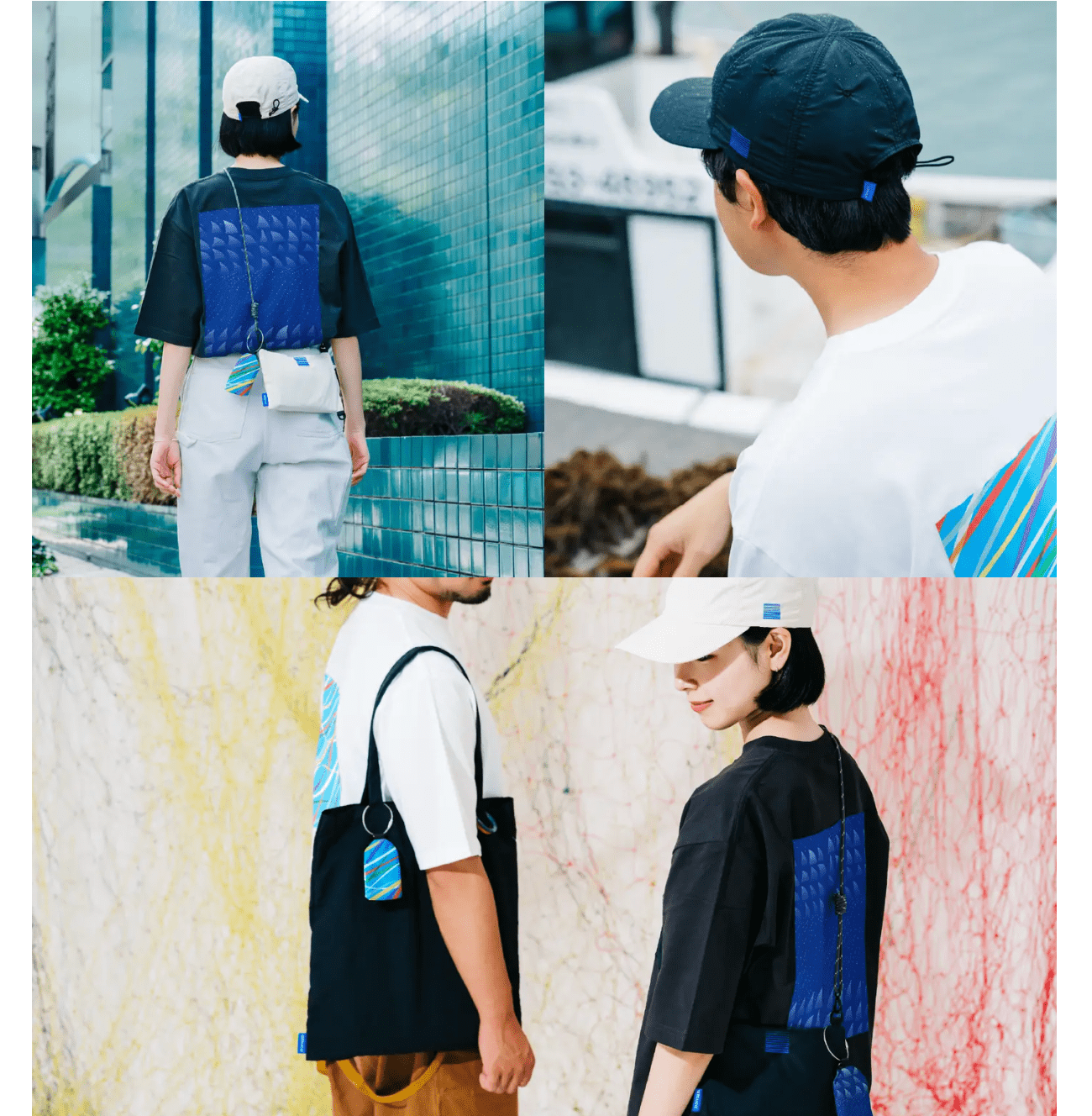古材のリユースに注目が集まる昨今。そのトップランナーとして2016年から活動しているのが、長野県諏訪市にあるReBuilding Center JAPAN(以下、愛称のリビセンと表記)です。
周辺地域の空き家や片づけ中のお宅から引き取った古材や古道具を販売するリユースショップ及びカフェの運営に加え、リノベーション、プロダクトの制作・販売など、地域資源の循環につながる事業を幅広く展開しています。
共同代表である東野華南子さんに、2016年の事業開始当初から現在までの展開についてお話をうかがいました。前後編の前編は、創業までの経緯、レスキューから販売までの流れ、カフェ併設の理由などをお届けします。
新婚旅行で訪ねたアメリカの「ReBuilding Center」がきっかけに
—リビセンを創業した経緯について教えてください。
リビセンを立ち上げる以前から、夫(東野唯史氏)と私は主に店舗などの空間デザイン・リノベーションを手掛けていました。
依頼のあった場所に出向き、その土地で寝泊まりしながら解体、デザイン、施工をして、完成したら次の場所に移るという、遊牧民のような暮らしをしていました。数カ月単位で全国を回っていたのですが、その現場周辺ではものすごい勢いで家が壊されて、古材が捨てられていたんです。

当時はインダストリアルデザインなどが流行していたこともあって、輸入の古材が人気でした。海外から古材が輸入されている一方で、日本のそれは捨てられている。この矛盾をどうにか解消できないかと感じていました。
そんなときに、新婚旅行でアメリカ・ポートランドにある「ReBuilding Center」を訪ねたんです。彼らの公共的な理念に感動し、日本でも同じようなスタイルで地域の資源を循環させることができれば、と思ったのがきっかけです。
帰国後にダメ元で、「名前とロゴを貸してほしい」とメールで依頼すると、すぐに快諾してくれました。それならと物件を探し始めたら2日で見つかり、交渉に行ったらその場で借りられることになったんです。本当に、トントン拍子で進んでいったので、もうやるしかない、という状況でしたね(笑)。
―お店を諏訪地域に構えた理由は、何かあったのですか?
私たちが2人で手がけた最初の空間デザインプロジェクトが、諏訪市内のゲストハウスでした。当時は東京に家があったのですが、その後も全国での仕事が決まっていたので、東京で家賃を払うよりもいいと考えて、下諏訪に引っ越していたんです。
一方で、諏訪の立地がリビセンのコンセプトに合っていた、という面もあります。私たちが資源だと考えている古材や古道具は地方に多いですが、ニーズはどちらかというと都市部にあります。地方だけど東京や名古屋などの大都市からのアクセスがいい長野県諏訪市は、好条件でしたね。
古材や古道具がレスキューされ、お店に並ぶまで
— リビセンでは、空き家などから古材や古道具を買い取ることを「レスキュー」と呼んでいますね。どのような流れでレスキューが行われるのでしょう。
家主の方から直接ご連絡をいただいて、私たちがレスキューに向かいます。最近は公式LINEから問い合わせがあって、やりとりしてから現場にうかがうことが多いです。
家屋の解体を伴うケースは全体の1割程度で、その他は片づけで出てきた家具、食器などのレスキューが中心です。また、直接店舗に持ち込まれるものも、全体の4分の1ほどあります。
レスキューしたものは掃除をして状態を整え、どこから来たのかわかるようにトレースする作業を行います。その後値付けをして、販売しています。ここ最近は、車で1時間以内の地域で月に60〜70件、年間800件以上のレスキューをしています。
— 月に60〜70件とは、すごい数ですね。
レスキュー数は年々増えています。みなさん自宅や空き家の片づけに困っているので、口コミでどんどん広がっているのだと思います。
あとは、実際に店舗があることも強みだと感じますね。事前にお店に来て販売されている商品を確認できると、どういうものがレスキューできるのかイメージがつきます。
レスキューを依頼される方々の心境は、実はとても複雑です。「こんなもの引き取れません」と言われたら傷つきますし、同時に、わざわざ足を運んでもらったのに買い取ってもらえるものがなかったら悪い、という気持ちも持っています。
店舗の存在が、依頼のハードルを下げている部分もあるのだと思います。
カフェをつくった理由は?
— お店で人気があるのは、どんなものですか?
売上ベースだと、食器が占める割合が大きいですね。その他は、木箱なども人気があります。リビセンの店舗に来て購入されるお客さんは、県内が半分、県外が半分ほどです。車で1時間圏内の長野や山梨にお住まいの方、東京・名古屋といった都市部の方などもいます。
そういう方々が「せっかく来たから何か買って帰ろう」と思ったときに、手に取りやすいのが食器類なんだと思います。日常生活に取り入れやすいのでしょうね。
—店舗で古材も販売されていますが、どういった方が購入されるのでしょう。
長野は移住者が多い地域で、自分で家具や雑貨などを作って楽しんでいます。その材料として、購入してくださる方が一定数いますね。
ただ、古材についてはお店での販売よりも、私たちがリノベーションで使用するほうが多いですね。今後はさらに広げていきたいと考えています。
—リビセンにはとても素敵なカフェが併設されていますよね。リユースショップとカフェという組み合わせはあまりないように思いますが、一緒に運営しようと考えたのはどうしてですか?
リビセンが「行きたい場所」になるためにはどうしたらいいかを考えたときに、自然と出てきたのがカフェでした。古道具だけだと、興味のない一般の人には「自分には関係ない」と思われがちです。でも、カフェがあるなら「行ってみたい場所」になりやすい。
私自身が以前全国チェーンのカフェで働いていた経験があり、飲食店経営の全体像をある程度把握していました。だから始めやすかった、という要素もありました。
—確かに、カフェがあると立ち寄りやすいですね。現在はどれくらいの方がリビセンを訪れているのでしょうか。
年間で約3万人です。これは購入者の数なので、ふらっと立ち寄った方も含めると、もっと多くなると思います。帰省の際に「通り道だから」と来店してくれるお客さんもいて、そうした方々に支えられて、ここまで継続してこれたと感じています。
—————————
後編は、エリアリノベーションによって変化する周辺地域、リビセンのノウハウを伝える「みたいなスクール」で全国に広がる古材リユース、などについてお届けします。