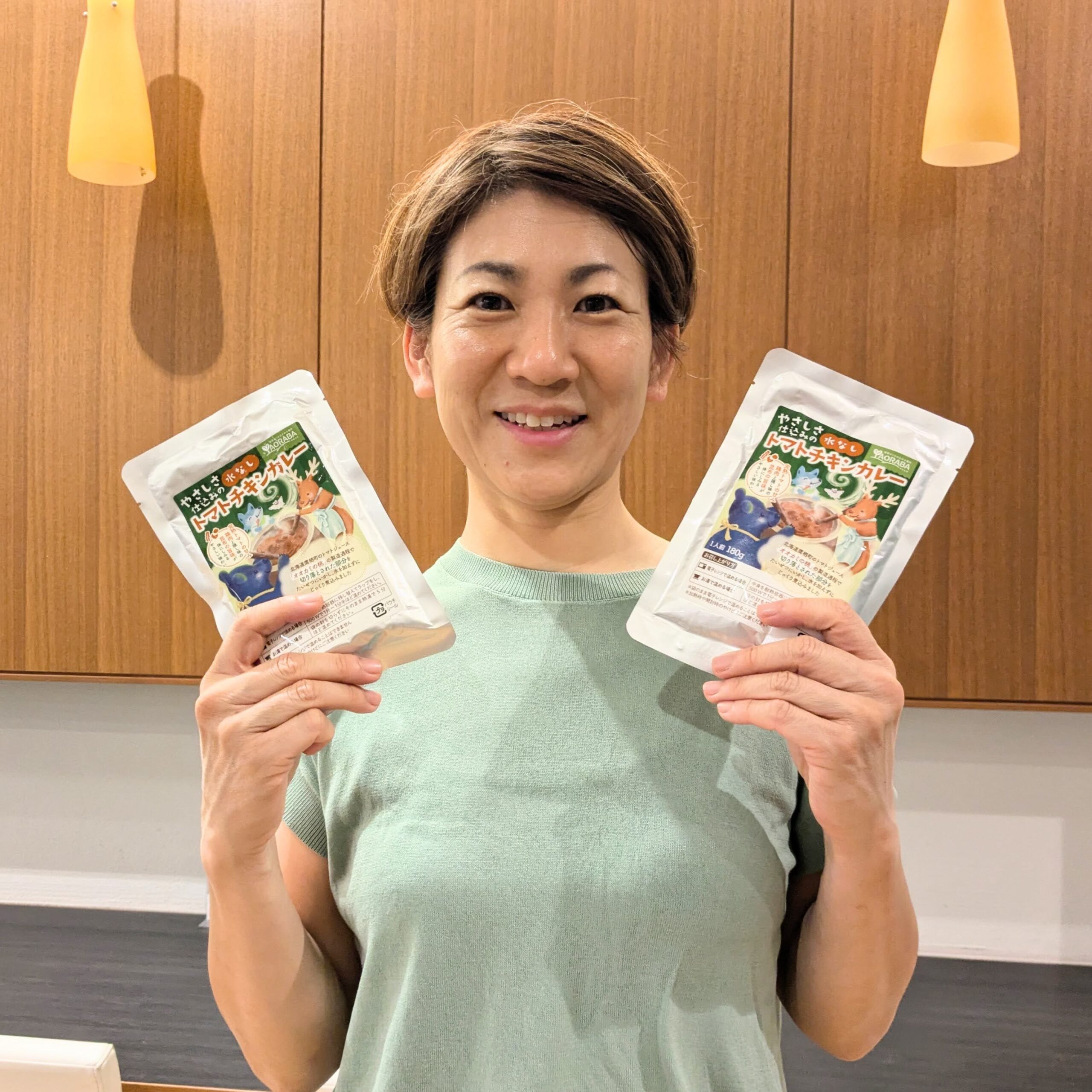福岡市は2012年に「スタートアップ都市ふくおか」を宣言し、スタートアップ支援に力を入れてきました。この中心的な役割を担う施設が同市にある「Fukuoka Growth Next」です。ユニコーン企業を生み出すべくさまざまなスタートアップ支援を行っています。
なかでも環境系スタートアップとして注目を浴びているのが株式会社ベンナーズ。「未利用魚」と呼ばれる廃棄されるはずの魚を、食材へと生まれ変わらせる取り組みを手掛けます。
すべての魚の価値化を目指して株式会社ベンナーズでは未利用魚を積極的に活用し、これまで利用した未利用魚は307トン、過去5年間の累計会員数は5万人にのぼります。廃棄されるはずの魚がなぜ、ここまで受け入れられているのでしょうか?
フードロス削減にとどまらない「未利用魚」の可能性について、株式会社ベンナーズ 代表取締役 井口剛志氏にお話をお聞きしました。
ソーシャルスタートアップ支援にも力を入れ始める「Fukuoka Growth Next」
「Fukuoka Growth Next」(以下、FGN)は、福岡市の官民協働型スタートアップ支援施設として2017年4月に開設されました。福岡市の雇用創出や地域経済の発展への貢献、将来的なユニコーン企業の創出を目標として、インキュベーションオフィスだけでなく、さまざまな支援プログラムをスタートアップに提供しています。

FGNに入居するスタートアップは149社(2024年度末時点)。脱炭素やCO2回収、フードロスなどの分野に取り組むスタートアップも入居しており、2024年度からは社会や地域の課題解決に取り組むソーシャル分野のスタートアップの支援に、さらなる力を入れています。
今回ご紹介する株式会社ベンナーズは、このFGNに入居していたスタートアップの一社です。現在は福岡市東区に本社を構え、未利用魚をミールパックにして届けるサブスクリプションサービス「フィシュル!」(以下、フィシュル)を展開しています。
ここからは、株式会社ベンナーズの井口剛志氏にお話を伺います。
「未利用魚」とは?
—まず、フィシュルで扱う「未利用魚」がどのような魚なのか教えてください。
「未利用魚」とは、サイズが不揃い、十分な水揚げ量がなくロットがまとまらないといった理由から、流通に乗せられない魚のことです。マイナーなために全国的になじみがない魚、加工しにくい魚なども含まれ、味とは関係ない理由から避けられてきました。
例えば、みなさんもご存知の「ボラ」という魚があります。卵巣がカラスミの原料として使われていますが、ほかの部位は捨てられていました。ボラは汚い水でも生きられる魚であるため臭いイメージがありますが、沖合いで獲れるボラは「沖ボラ」と呼ばれ、全く臭みがなくておいしい魚なんです。

ー日本では「未利用魚」の割合はどれくらいなのでしょうか。
日本では、「未利用魚」は総水揚げ量の3〜4割を占めると言われています。定置網漁や底引き網漁の場合に発生しやすく、さまざまな魚をまとめて獲るために売れない魚も一緒に獲れてしまうのです。「未利用魚」は、漁師の方が食べるなど漁港周辺で消費されることもありますが、かなりの量が廃棄されているのが現状です。
未利用魚に着目したサブスクサービス「フィシュル」

—フィシュルの取り組みについて教えてください。
フィシュルは、のせるだけ、焼くだけ、茹でるだけ、というコンセプトで、おいしく味付けした魚をミールパックで届けるサブスクリプションサービスです。国産で旬の未利用・天然魚であることを大切にしています。
—未利用魚の入手から加工、販売までの流れを教えてください。
未利用魚は、直接、漁師の方から買い付ける場合もあれば、仲買人の方から買い付けることもあります。水揚げ後の魚はすぐに加工することが私たちのこだわりです。そのため、日本各地の漁港近くに加工場を設置。自社工場(福岡)以外に、大阪や東京を含め全国13カ所にパートナー加工会社があり、地元で仕入れた未利用魚を各加工場で加工しています。
加工場では、仕入れた魚の下処理からカット、味付け、瞬間冷凍まで行い、それぞれパックに入った状態で製品としてお客様のもとへお届けします。各地域にこうした加工場を持つことで、鮮度の高い状態で商品を提供することができるのです。

コロナ禍で誕生。すべての魚の価値化を
—フィシュルはどのようなきっかけから生まれましたか?
もともと、実家が水産加工を営んでいて水産業にはなじみがありました。2019年に魚の売り手と買い手をつなぐプラットフォーム「マリニティ」を立ち上げ、魚を仕入れるために私自身も港へ足を運んでいたんです。未利用魚の存在を知ったのはそのときですね。大量の廃棄される魚をなんとか活用できないかという現場の声をよく聞きました。それ以来、有効に活用できる道を探っていたんです。
そんなとき、コロナ禍で外食産業が停滞し、魚の消費先がなくなってしまいました。そこで考えたのが、未利用魚を加工し直接お客様に届けるBtoCモデルです。未利用魚を活用したサブスクサービスとして、2021年にフィシュルをスタートしました。FGNに入居していたのはちょうどこれら2事業の立ち上げ時期である、2019年から2021年までです。

ーこれまでにどれくらいの未利用魚を活用できましたか?
2021年のサービス開始以来、307トンの未利用魚を商品化しました。活用した魚種で言うと、未利用魚以外も含めて50種類を超えています。
—日本では漁獲量が大幅に減少する状況で、3〜4割という未利用魚の割合は大きいですね。
将来は日本の漁獲量だけでは需要を賄い切れないのではないかという危機感を抱いています。だからこそ私たちは、すべての魚の価値化を目指しています。未利用魚が抱える「臭み」「捌きにくい」といった問題を、加工や流通技術により解決し資源として有効活用していきたいです。
また、未利用魚の認知度向上にも力を入れています。これまで「食育」をテーマに、小学校での出張授業や、大人向けの未利用魚の調理・試食体験を開催してきました。「魚=資源」という認知を広め、水産業についても学びを深めてもらえたらと考えています。
廃棄されていた魚で地域課題を解決
—仕入れ先や加工場は各地に展開されていますが、未利用魚の活用は漁師の方からすぐに受け入れられましたか?
各地の漁港を訪ね歩き仕入れ先と加工場を開拓しましたが、その過程で感じたことは、未利用魚の活用は自社工場のある福岡に限らず各地の加工場が抱える課題だということです。廃棄されていた魚に新たな価値を見出すフィシュルのアイデアは、漁師の方や加工場で働く方にとって確実な収入源となり、地域の雇用にも貢献できます。漁業関係者にとって受け入れやすかったのだと思います。
—地域雇用のほかには、どのような課題を解決できると考えていますか?
フィシュルは、すべての魚の価値化を目指して、資源を無駄にせず食材へ有効に活用する取り組みです。フードロス削減につながるのはもちろん、SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」を果たすことができると思っています。
また、特定の魚種だけを狙って捕る乱獲が問題になっていますが、すべての魚に価値があれば、乱獲を減らせるのではないでしょうか。値段のつく大きな魚だけでなく規格外の魚や見た目の悪い魚などもバランスよく獲れば、海の生態系にもいい影響を与えます。これはSDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」につながると考えています。

持続可能な水産業を見据えて
—現在抱えている課題はありますか?
大きく分けて2つあります。ひとつは、年間を通じて安定的に品質と供給量を保つことです。魚は季節によって獲れる量が変わり、近年は気候変動の影響で魚が獲りづらくなっています。同じ魚でもそれぞれ匂いの強さなども異なるため、満足いただける一定のおいしさで安定した供給ができるよう、加工技術の向上が必要です。
もうひとつの課題は、物流コストの高さです。冷凍便で配送するため、物流コストが高くなってしまいますが、なるべくお客様に負担をかけないように工夫を重ねています。
—今後の展開について教えてください。
まずは、安定供給と品質保持を徹底していきます。そのために加工拠点を増やして、自社工場も増設する予定です。また、フィシュルはオンラインのサービスなので、消費者とのリアルな接点の場も作っていきたいと考えています。具体的には「玄海丼」という海鮮丼店を京都市内に2店舗展開し、未利用魚に限らずマグロといった当社の魚のおいしさを体験してもらう機会をつくっています。

また、将来的には海外展開も視野に入れています。日本の水産資源だけでは需要を満たせなくなる可能性もあるため、海外の漁場や加工場の活用も検討を始めたところです。
どの魚も限りある海の資源。有効な活用方法を広め、消費者、漁業従事者、自然環境を含めた社会にとってよい、持続可能な水産業をつくっていきたいです。