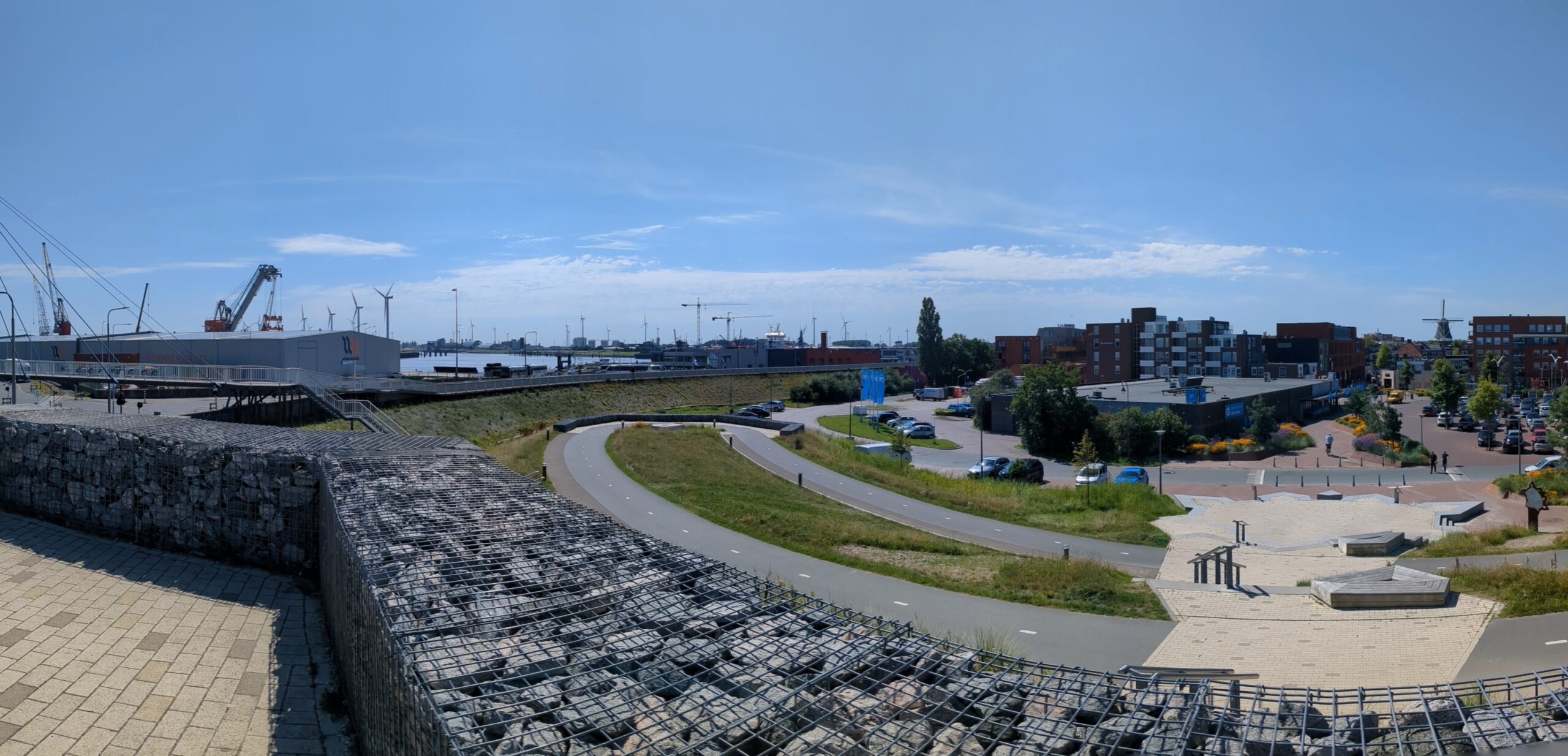急増するアルミスクラップ輸出とEUの危機感
欧州連合(EU)のアルミニウム業界は、域外へのアルミスクラップ輸出が過去最高に達したことを受け、欧州委員会に対し30%の輸出関税導入を要請しました。2024年には126万トンが輸出され、5年前から約50%増。その大半はアジアに流れています。
背景には、米国がトランプ政権下で導入した輸入関税があります。アルミに50%、スクラップに15%という関税設定により、米国向けの取引が減少。その結果、アジア市場がEU産スクラップに強く依存するようになったのです。
欧州アルミニウム協会のポール・フォス事務局長は「スクラップ業者が高値をつけるアジア市場に売るのは自然だが、欧州の戦略的利益を守るために公共政策が必要だ」とも言及しております。
「都市鉱山」の象徴
アルミスクラップとは、使用済みの飲料缶や自動車部品、建材、電子機器などから回収されたアルミニウムのことを指します。
アルミは一度使用されても繰り返しリサイクルしても特性を維持しやすく、繰り返しリサイクルできる「優等生」素材。特にリサイクル工程では、新たに鉱石(ボーキサイト)からアルミを精錬する場合に比べ、約95%少ないエネルギーで済むことが知られています。
そのため、アルミスクラップは「都市鉱山」と呼ばれる資源循環の象徴的存在であり、脱炭素社会に向けた重要なピースです。
アルミスクラップは「資源循環」と「脱炭素」の要
アルミスクラップは単なる資源ではありません。アルミをリサイクルすることは、CO₂削減の切り札でもあります。EUでは既に7億ユーロを投資し、リサイクル炉の処理能力を1,200万トン規模に拡大中。安定的なスクラップ供給がなければ、この投資の意味も薄れてしまいます。
一方で、リサイクル業界団体EuRICは「輸出増の背景には国内需要の低迷や混合スクラップ処理能力の不足がある」と指摘。単純に「輸出規制」だけをかけても、循環システムの持続性は確保できない可能性があります。
日本にとっての示唆
日本でも使用済み金属資源の海外流出は課題です。スクラップの価値が国際市場で高まる中、国内での循環をどう促すかが問われています。
EUの議論は「価格競争力を理由に資源が域外へ流出するリスク」と「国内産業の持続性」をどう両立させるかを浮き彫りにしました。
資源循環の設計には、単なる規制だけでなく、リサイクルインフラ投資、需要創出、製品設計段階からの循環性確保といった多層的なアプローチが必要だといえるでしょう。
参照