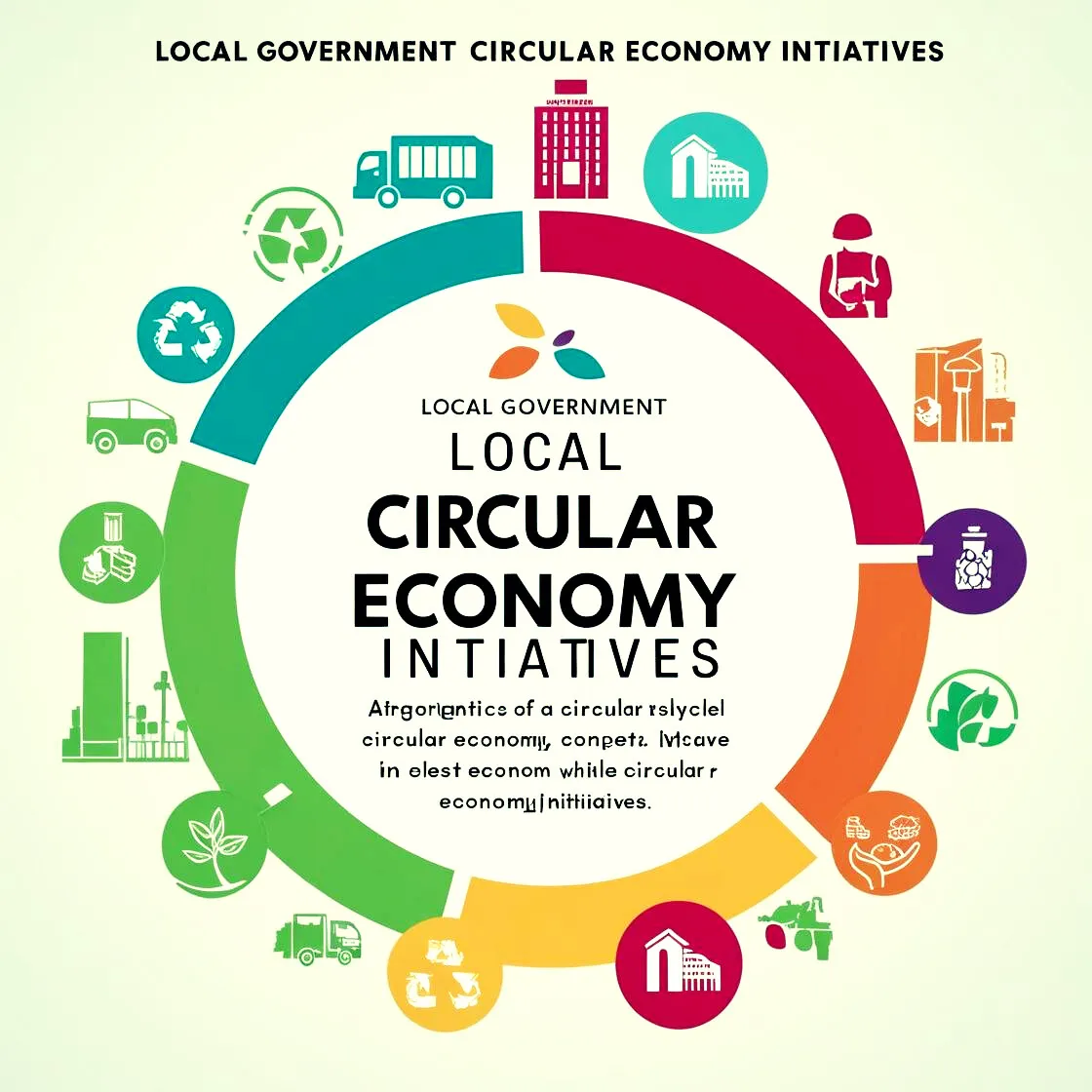産廃の卵の殻を原料にした「プラシェル」「シェルミン」「カミシェル」というエコ製品を世に送り出した株式会社サムライトレーディング。
代表取締役の櫻井裕也氏は、自社の製品開発と併行して「エコ玉プロジェクト」を立ち上げました。これはサムライトレーディングはじめ、埼玉県内に事業所をもつ企業3社が中核となり、卵殻製品の普及とともにSDGsの推進を目指す取り組みです。
任意団体ながら、多数の企業のほか金融機関や自治体も巻き込んだ官民一体の運動に発展し、県境を越えた広がりを見せています。
SDGsに共鳴する企業・自治体・業界団体をネットワーク
— 「エコ玉プロジェクト」の立ち上げについて教えてください。
私が委員長を務め、緩衝材のカネパッケージ株式会社や青果卸の株式会社ベジテックとともに、2019年に立ち上げました。
会員になる条件は、「プロジェクトのポスターを必ず事業所に貼る」「SDGsの17項目の1つでもいいから取り組む」「講演活動の際にSDGsの取り組み事例を出す」という3つだけです。年会費はなく、賛同できる人だけに参加してもらう緩やかな体制にしました。そのほうが迅速に物事を決めて実行に移すのに向いていますから。

— 参加者は企業、自治体、金融機関、業界団体と幅広いですね。どのようにして募ったのですか。
埼玉県が主催する渋沢栄一ビジネス大賞を受賞したのが、一つのきっかけになりました。プラシェルが2019年(奨励賞)、カミシェルが2020年(大賞)に受賞し、埼玉県の経済同友会で講演をすることになったのが大きかったです。そこで県内の企業や金融機関とのつながりができました。
また、県外企業の参加は、食品会社を経営していた頃から交流のあるシダックスの志太勤一会長(当時)の協力が影響しています。志太会長の名前が強力な後押しとなって、参加を決めた企業は少なくありません。
自治体の反応はさまざまですが、埼玉県は渋沢栄一ビジネス大賞を主催していることもあり、無条件で「渋沢の精神として参加するべきです」と言っていただきました。また、地元の桶川市や、私が以前経営していた食品会社のある鴻巣市、県内でも特に環境意識の高い入間市は、市長に直接話をさせてもらい、協力をいただきました。
自治体はメールや人を通じた間接的なアプローチではなかなか進まないので、直接会って「どうですか」と話をするようにしています。また中小企業診断士協会のように講演を通じてご縁ができ、参加につながった団体もあり、現在では参加企業・団体が50を超えるまでになりました。
名刺1箱で環境保全ができる
— 具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか。
第1弾として名刺の受注から始めました。名刺の用紙はカミシェルです。木材パルプと卵殻を原料にしたFSC認証紙で、一般的な名刺と比べて製造時のCO2排出量が20%ほど少ないのです。
名刺1箱100枚あたりの製造時の排出CO2は約12gですが、発注をいただくと、名刺100枚につきマングローブ1本をフィリピンの海岸に植樹します。1本のマングローブは少なく見積もって年間約10kgのカーボンオフセットを可能にするので、仮にマングローブが20年間生きながらえるとすれば、名刺1箱12gの排出に対して、200kgのカーボンオフセットが可能になるという計算です。
植樹の効果はCO2の吸収だけではありません。マングローブは水辺に根を張るので、魚のすみかになって生物多様性の保護につながりますし、さらに成長すると林になって、台風や津波の際の防災・減災に役立ちます。また、マングローブは手入れが必要なので、現地雇用も生み出します。
こういった仕組みを自分一人で考え、実行に移すのはとても大変ですが、名刺を発注するだけで環境保全や現地雇用に貢献できるとわかれば、やってみようと思う人は多いのではないでしょうか。

家庭の廃食油が地域の燃料に
— エコ玉プロジェクトは埼玉県を中心に広がりを見せていますが、地域と連携した取り組みにはどのようなものがあるのでしょうか。
家庭から出される使用済み食用油の回収を行っています。これは私が顧問をしている会社の事業を参考にしており、もともとの事業モデルは、関東一帯のスーパーや飲食店で発生する廃食油を回収し、SAF(航空燃料)などに加工してエネルギー会社に販売するというものでした。その事業のかたわらいろいろ調べるうちに、家庭から排出された廃食油が問題を引き起こしていることがわかりました。
家庭の廃食油は少量だからと排水管に流してしまう人が少なくないのですが、油は冷えると固まり、配管の内側に詰まってしまう。それが大雨の際に下水が溢れ出す原因になるというのです。昨今の気候変動で大雨が多発する中、これは問題だということで、エコ玉プロジェクトでは家庭から出る廃食油を回収して再生するモデルを考案しました。
— 一般家庭から使用済みの油を回収するルートを作るのは難しく感じますが……。
自治体や企業の協力が得られれば、決して難しいことではありません。まず、スーパーや自治体の施設などに回収ステーションを設置して、家庭から出た油をペットボトルなどで持ってきてもらいます。それを私たちがトラックで回収し、精製して販売するというモデルです。廃食油の回収は無料ですが、精製した燃料の販売益があるので、それが私たちの収益となります。自治体に予算をとってもらう必要はなく、市民への呼びかけだけをお願いすることになります。
これは入間市への提案として、市長に直接事業モデルの説明を行ったところ、その場で「やりましょう」と即決していただきました。
その後、連携協定を結んで回収を始めています。入間市の家庭から出る廃油を回収して燃料にし、入間市に入ってくるトラックをその油で走らせるという、エネルギーの地産地消を意図したものです。市民の油で市内のトラックが走るという循環性は、市民にも親しみを持ってもらえるでしょう。 現在は入間市だけですが、自治体と市民、油を回収する私たちにとってもメリットの多い取り組みなので、今後はぜひ他の自治体にも広げていきたいと思っています。

市民の立ち寄りやすい場所に設置している
着手しやすい単一素材の資源循環
— 他にも資源循環の取り組みをされていますね。
物流会社のセンコー株式会社と協力して、樹脂製ストレッチフィルムのリサイクルを行っています。同社の物流センターでは、商品を傷つけないようにストレッチフィルムでぐるぐる巻きにしますが、出荷時にはそれを全部外すので、そのままではフィルムがゴミになってしまいます。
しかし、ストレッチフィルムは単一素材なので、再生・再利用に向いているのです。私たちはこのストレッチフィルムを全部回収してゴミ袋にリサイクルし、またセンコーに売り戻しています。そのゴミ袋にストレッチフィルムを入れて回収し、また再生するという循環です。分別の必要がなく、素材の洗浄も不要で、極めてロスの少ないリサイクルです。
ほかには、アパレル企業からハンガーを回収して、その企業が販売する枕の中身のパイプ素材に再生するなど、企業内で完結する循環モデルの構築をお手伝いしています。
ストレッチフィルムにしてもハンガーにしても、「単一素材だけ回収できる」「相手が限定されていてクローズドの循環ルートがつくれる」の2つの条件が揃えば、リサイクルは比較的容易です。そこに宝の山があるといってもいいでしょう。
エコ玉プロジェクトのポスターでは、白い卵の中に金色の卵がいくつか混ざっています。身の回りにあるものが対応次第で金の卵に化ける。それは成功する循環経済のあり方に通じるのではないでしょうか。
今後も柔軟な発想を忘れず、多くの賛同者を得てできあがったエコ玉プロジェクトのネットワークを活かして、SDGsに貢献する活動を続けていきたいと思います。