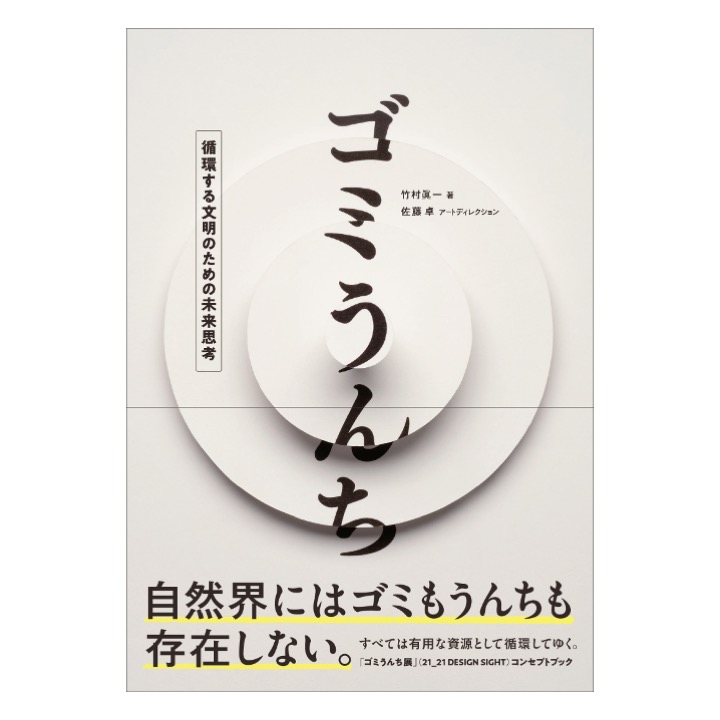バイクやボート、電動アシスト自転車など、新たな需要を創出するプロダクトを通じて自然の中での感動体験を提供してきたヤマハ発動機株式会社。近年「地球がよろこぶ、遊びをつくる」をミッションに掲げている同社で、共創・新ビジネス開発部の臼井優介氏が乗り出したのは「マイクロプラスチック回収機」という新たなビーチクリーン・ギアの開発。海洋ごみは地球規模の環境問題でありながら、主な対策がビーチクリーン活動というボランティアに委ねられていることに問題意識を感じたという臼井氏に「従来のトングでは拾いきれないマイクロプラスチックを楽しみながら回収できたら」という開発意図を伺いました。
「地球がよろこぶ、遊びをつくる」
— ヤマハ発動機の中でこのプロジェクトはどのような位置づけなのでしょうか?
臼井(以下略):ヤマハ発動機は70年に渡って、バイクやボート、電動アシスト自転車など、自然の中で楽しむ製品で新たな需要を創造してきました。そのため地球環境の変化に対する感度が高いんです。今は「地球がよろこぶ、遊びをつくる」というミッションを掲げて、サステナブルの先にあるリジェネラティブな事業創出を目指しています。
昨年4月に入社して知ったのは、トップダウンではなくボトムアップの会社だということ。企業としての取り組みと個人としての取り組みの境界が曖昧で、そこから多くの新規事業が生まれてきました。
私が所属するのは技術・研究本部共創・新ビジネス開発部の「共創推進グループ」。オープンイノベーションを推進し、0から1を作り出す部署です。
今回私が取り組んでいる「マイクロプラスチック回収機」もヤマハ発動機の「リジェラボ」という拠点で自治体や企業、研究者やローカルのプレイヤーたちとの共創で新たなモノ作りに取り組んでいるものの、ひとつになります。
— 臼井さんがマイクロプラスチック回収機の開発に取り組んだきっかけを教えてください。
脱炭素モビリティ開発の視察で行った沖永良部島で生まれて初めてビーチクリーンに参加したのがきっかけでした。海流の影響で大陸からの海ごみが大量に押し寄せる現状と、島民の方々が日常的に海岸清掃を行っている姿を目の当たりにしたんです。衝撃でした。
神奈川に戻ってからビーチクリーンイベントにも参加するようになりました。やってみてわかったんですが、トングで足元に広がる数えきれないマイクロプラスチックを回収するのは限界があります。無力感も覚えましたが、細かなマイクロプラスチックは魚や鳥が誤食する可能性も高く、食物連鎖を通じて人間の体内に入っているという報道もあります。なんとかしなければと自分なりに問いを立てたのが始まりでした。
— この問題にどのように取り組もうと考えたのでしょうか?
ビーチクリーンに取り組む中で、いくつかの課題を発見しました。活動がボランティアに頼っていること、マイクロプラスチックの回収が厄介なことでした。多くの方が感じているように「トングに代わる道具」が必要だと感じたんです。やったことのある方は誰もが感じると思いますがマイクロプラスチックを拾うのは本当に地味で楽しくない(笑)。ならばそこにヤマハが掲げる「地球がよろこぶ、遊びをつくる」という"楽しさの要素"が加味できれば、好循環が生まれ、世界がより良くなっていくのではないか。また、海洋ごみ対策が2030年までに5000億円規模の市場になると推測してグローバルマーケットでのビジネスにもなるのではないかと考えました。
タイの海ごみ回収機の動画がきっかけに
—ここまでの開発の歩みを教えてください
かながわ海岸美化財団の柱本健司さんが見せてくれた、タイの海ごみ回収機の動画を参考に初号機を作ることにしました。横浜の日本発条株式会社さんが趣旨に賛同してくださり、社会課題の解決に取り組む共創パートナーとして初号機を製作してくれたんです。砂浜を走らせながら砂とともに海ごみを回収。細かな網目から砂の粒子だけを排出する形でマイクロプラスチックを回収する仕組みです。

でも、海岸での実証実験は、思っていた以上にうまくいかなかった。改良していくために湘南工科大学とも連携。初号機を使った学生60名ほどによるワークショップも開催し、改善策をディスカッションしました。

そこで出たアイデアなども参考に、2号機では素材も見直し、軽量化。箱型にして、タイヤを大きくしたり、引き手の角度を調整できるようにしました。また、上部に熊手のような爪をつけて砂を堀り上げながらゴミを浮かせる機構も追加しました。

その2号機で見えた新たな課題点を改良し、さらなるコンパクトと軽量化を実現。かつ、未発表の新しい機構を付記したのが今日、実証実験を行う、2.5号機です。私も初めて実機と対面するんですが、わくわくしています。

共創パートナーである日本発条株式会社のみなさん、
製品のデザインを担当する株式会社日南クリエイティブベースのみなさんが
海ごみが散乱する海岸に集まって実施されました
(※新機構が特許出願予定の為、製品にはモザイクが入っています)
大切なのは"そこに楽しさや感動が生まれるか?"


—新製品の実証実験というよりは、夏の海に遊びに来たような和気あいあいとした雰囲気さえ漂っているように感じますね。
従来のエコ活動のように我慢するのではなく、遊び心や楽しさを重視することで持続可能な活動にしたいという思いが強いのが今回の開発ですからね。
環境保全活動に繋がる今回の製品開発においても"そこに楽しさはあるか?"、”そこに感動は生まれるか?"を大切にしています。それにはまず、自分たちが開発の段階から「本気で楽しんで、感動すること」。そのスピリットこそが、ヤマハ発動機が70年に渡って使う人を楽しませる、感動させる、本気で遊ぶ製品を作り続けることができた理由だと思っています。

会議室ではなく海ごみの現場で開発を進めている
—かながわ海岸美化財団の柱本さんはこの取り組みについてどんな思いを抱いていますか?
柱本:世界では海ごみは放ったらかしなのがほとんどです。おかげ様で神奈川県には16万人くらいビーチクリーンのボランティアがいます。でも、人はいるけど、良い道具がない。マイクロプラスチックはトングで摘まむか、ザルで分別するしかない。うちとしてもなんとか形にならないかなと。回収したプラスチックを買い取ってアップサイクルして下さる企業も出てきていますので、良い循環が生まれればと思っています。
—臼井さん、今日実施した2.5号機の実証実験にはどんな手応えがありましたか?
まだ3合目くらいでしょうか。タイヤのグリップ力が弱かったり、湿った砂が詰まりやすいなどまだまだ改善しなければならない点はありますが、マイクロプラスチックという課題を解決するための存在していなかった道具。トングに代わるスタンダードを作るという挑戦ですからね。試行錯誤ですが、今までの試作機にも多くの問い合わせを頂いている。完成すれば多くの人に喜んでもらえるはずだと信じています。
— 最終的にはどのような製品にしていきたいと考えていますか?
社内では自動運転モビリティと組み合わせてはどうかという声もありますが、高性能だけど100万円するような製品では普及しない。マイクロプラスチックの問題解決に関しては、トングに代わるシンプルで手頃な価格の道具こそが、世界でも最もニーズがあると考えています。9月に大阪・関西万博の「BLUE OCEAN DOME(ZERI JAPAN)」で開催されるイベント「BLUE Challenge 2025」で、コンセプト機となる3号機を発表する予定ですが、一番大切にしているのは、"この道具で遊ぶ世界を作るんだ"というヤマハのスピリット。自然の中での感動体験こそが、自然を大切にしようという自発的な思いに繋がっていく。自分でもビーチクリーンをやってみて改めて感じましたが、環境活動というのは道徳心や正義感だけじゃ続かない。だからこそ「地球がよろこぶ、遊びをつくる」道具を生み出したいと思っているんです。ひとりでも多くの人に遊びを通じて自然の素晴らしさを体験して貰える道具を。