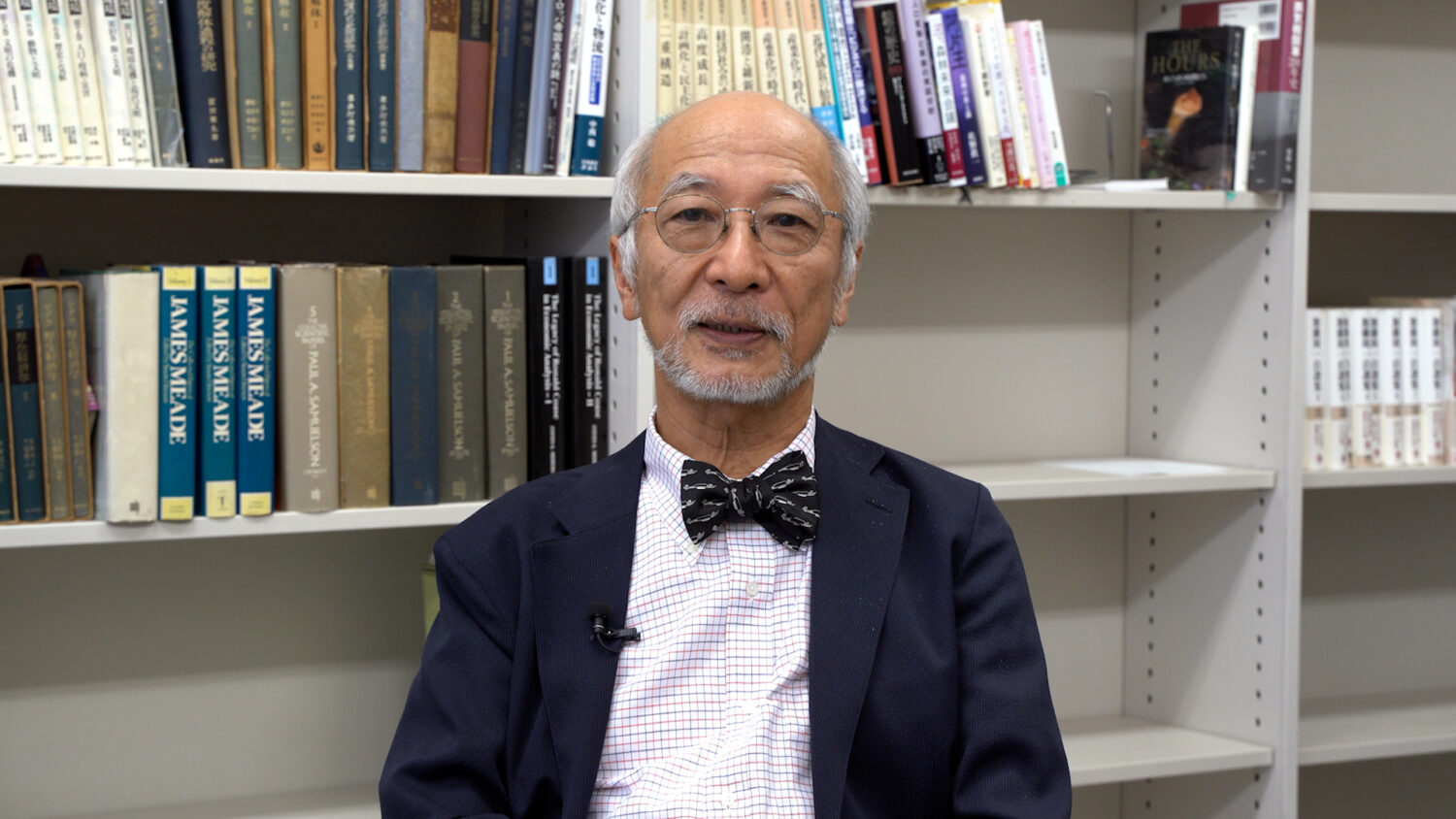日本のプラスチック資源循環に関する課題と展望について、第一人者である東海大学学長補佐・経済政治学部教授の細田衛士先生に話を伺いました。プラスチック勉強会の司会を務める株式会社トーマス代表の滝口氏がモデレーターとなり、国の政策動向から資源循環の現場が直面する課題、そして今後あるべき姿まで、幅広い視点からお話しいただきました。循環経済の実現に向けた道筋と、業界関係者が取り組むべき連携協力の重要性について、貴重な示唆に富んだインタビューとなりました。
日本のプラスチック資源循環戦略の現状と課題
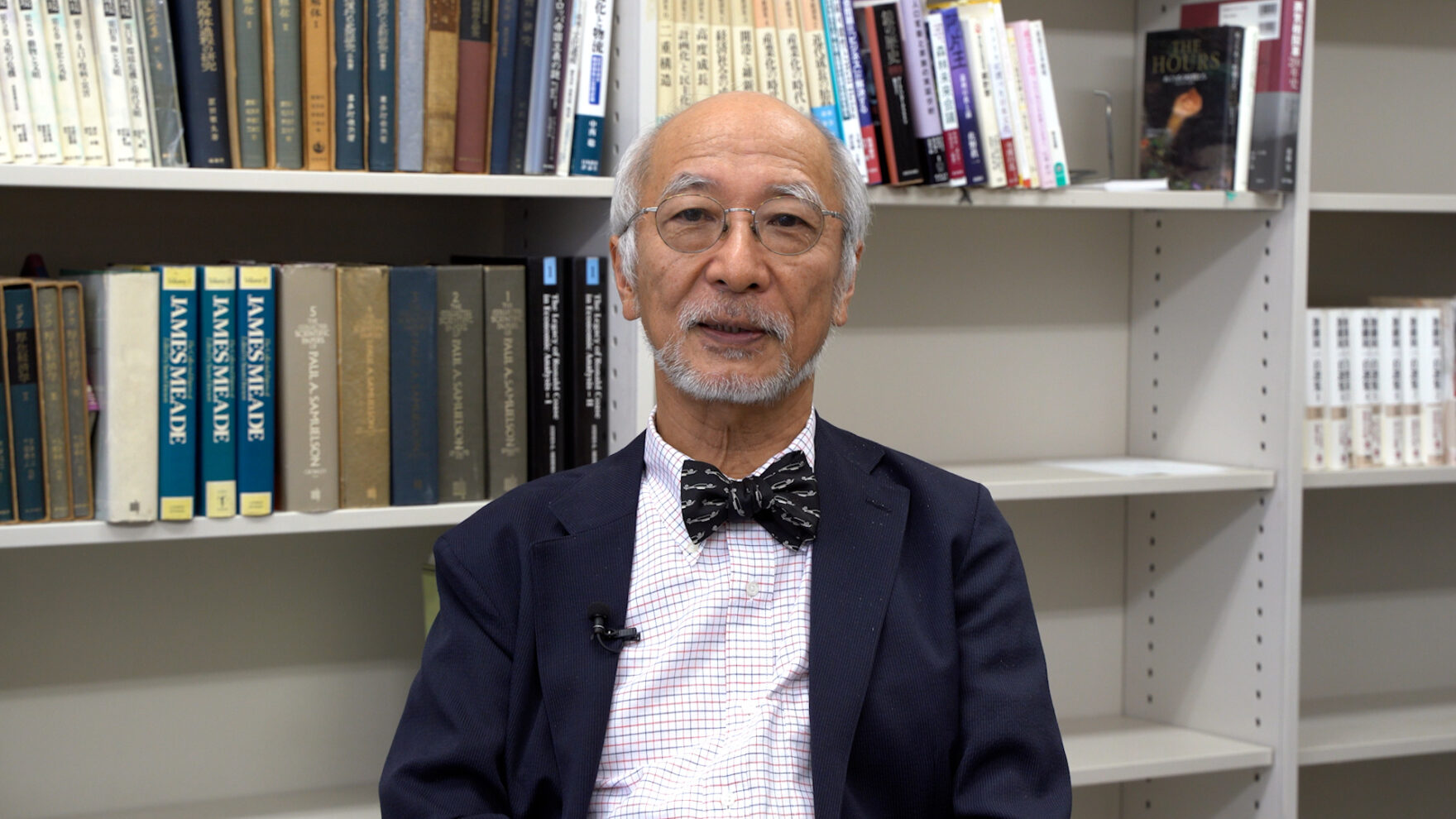
— 近年、プラスチック資源循環に関して国家戦略や資源安全保障といった言葉が頻繁に使われるようになりました。日本のプラスチック資源循環戦略の進捗状況について、先生は現状どのように評価されていますか?
この問題は今最もホットな議題の一つになっています。特に昨年、第5次循環基本計画が閣議決定され、サーキュラーエコノミーを国として打ち出すことが決められました。経済安全保障、国際競争力の強化、生活の質の安定、地方創生など、あらゆる面で資源の高度な循環利用・再生利用が絡んでくることが国策として示されました。その中で特にプラスチックの循環利用が重要視されています。
ポイントは2つあります。1つ目は、これまで日本ではプラスチックがマテリアルとしてあまり循環利用されてこなかったという点です。フレークやペレットになっても使ってもらえず、海外に出て行き、海外で再生利用される状況でした。日本での有効利用はほとんどがサーマルリサイクルでした。これでは資源問題にしっかり対応するという観点からはまずいでしょう。
2つ目は、EUの新しいELV規則で、自動車にリサイクルプラスチックを一定割合使うことが義務付けられる見通しとなったことです。全体の20%をリサイクルプラスチックとし、そのうち15%は使用済み製品由来でなければならないという厳しい縛りです。これは日本車をEUに輸出する際にも適用されるため、今まで再生プラスチックの供給を進めてこなかった日本も、世界の中で資源を有効に利用しなければならないという要求に直面しています。
しかし、使用済みプラスチックを回収し、分別・洗浄してフレーク、ペレット、コンパウンドにし、成形メーカーに渡して使ってもらうという流れがまだ十分に構築されていません。これが現在の大きな課題です。
プラスチック新法の課題とEPR導入の議論

— 2022年に施行されたプラスチック資源循環促進法では、製品プラスチックのリサイクル費用にEPR(拡大生産者責任)が全面的に適用されていません。この点について先生はどのような背景や理由があったとお考えですか?
この法律を作る際、私も委員の一人として参加しました。当然EPRをどう適用するかが議論になりました。EPRを導入することで責任の所在が明確になり、フローをコントロールできるという大きなメリットがあります。お金の問題だけでなく、フローのコントロールこそが最も重要であり、それができればお金はついてくるものです。
しかし、プラスチック新法にはEPRが従来の形では入っていません。なぜかというと、EPRの基本的な発想は「製品」に対するものだからです。容器包装や自動車、家電製品などの場合、ブランドオーナーが特定でき、その責任が連鎖してフローをコントロールできます。しかし、プラスチックは素材であり、車にも家電にも容器包装にも、さらにはクリーニング屋のハンガーやバッグにも使われています。このように様々な形で使われるプラスチックに対して、誰に責任を取らせればフローをコントロールできるのかという点が難しいのです。
そのため、今回は従来型のEPRは導入されず、代わりに様々な関係者に「責務」という形で軽い責任を課し、自主的な取り組みでうまくやっていこうという形になりました。
自治体による一括回収の現状と課題
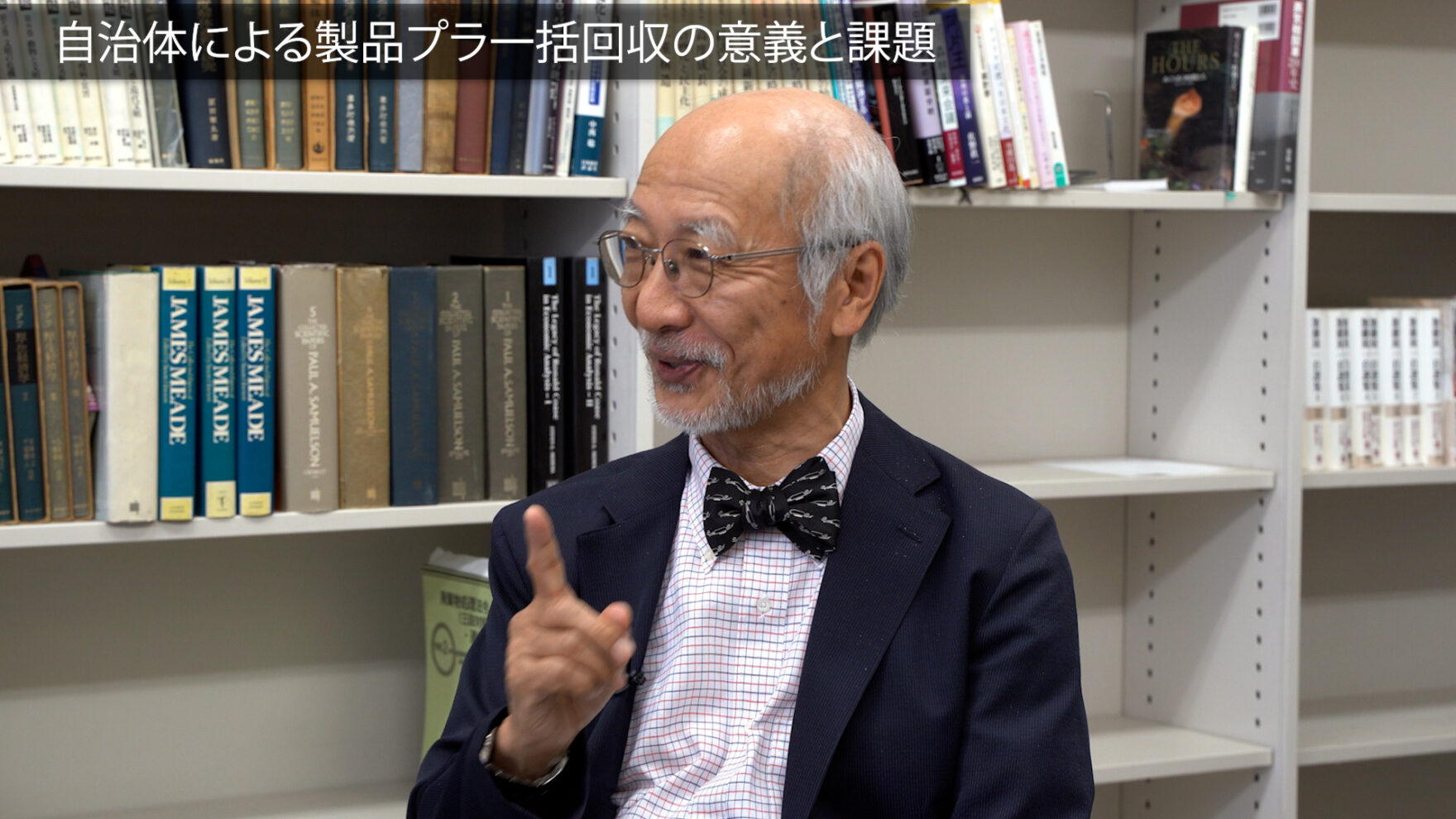
— 自治体によるプラスチックの分別収集は国から交付金を受けるための要件の一つとなっています。この政策についての課題はどこにあるでしょうか?
製品プラと容器包装プラの一括回収は、私の住む横浜市でも今年4月から始まりましたが、製品プラがあまり出ていないように感じます。まだ市民が慣れていないこともあるでしょう。
いくつか課題があります。例えば、なぜクリーニング屋のビニール袋やハンガーなどが容器包装リサイクル法の対象品目にならなかったのか、市民にはわかりにくいところがあります。また、ペットボトルはB2Bリサイクルが進んでいますが、その他のプラスチック容器包装については対象としている自治体はそれほど多くなく、マテリアルリサイクルもうまく回っていません。
プラスチック新法ではこれらを一括回収の形で対象に加え、製品プラも対象を拡大しました。市町村の既存のインフラを活用する点では効率的かもしれませんが、市民は容器包装と製品プラを分けて出すことも考えられ、それをソーティングセンターでどれだけうまく選別できるのかもまだ不透明です。今後の状況を見極める必要があります。
プラスチックリサイクルの将来展望と連携の重要性
— 最後に、廃棄物リサイクル・プラスチック資源循環の現場で働く方々へのメッセージをお願いします。
第5次循環基本計画の策定を受け、サーキュラーパートナーズという枠組みが国の主導で作られ、民間企業が参加して循環経済に向けた取り組みが始まっています。このような流れの中で、「大企業ばかりが優遇されるのではないか」という懸念の声もありますが、私はそうは思いません。
資源循環の世界では、現場で長年自助努力を続けてきた方々に知恵が蓄積されています。どうやって資源を集め、運搬するのかといったノウハウは、まさに現場で働いてきた皆さんが持っているものです。ただ、これからは今までのやり方だけでは不十分で、新たな連携が必要です。
回収から洗浄、フレーク化、ペレット化、コンパウンド、成形までの一連の流れをどうやって効率的に、より安く、より良くするかというスキームを全員が集まって考えていかなければなりません。つまり、知恵を合わせて連携協力することが重要です。私はこれを「コクリエーション(共創)」と呼んでいますが、クリエイティブなパワーを結集することを皆さんに期待しています。
業界の課題と将来への道筋

業界の大きな課題として、細田先生は使用済みプラスチックの「争奪戦」の可能性を指摘しました。EUの規制によって自動車メーカーがリサイクルプラスチックを大量に使用する必要が生じると、既存のリサイクル市場に大きな影響を与える可能性があります。
「自動車メーカーが本気でプラスチックを集め始めたら、今まで弁当の蓋などに再生プラスチックを使っていたメーカーに材料が行かなくなるかもしれません。これは米の問題と同じで、主食用の米がなくなると、せんべい用の米も不足するようなものです」と先生は警鐘を鳴らします。
このような混乱を避けるため、国がしっかりと全体を見て、各業界への波及効果を考慮した政策設計が必要だと先生は強調します。単なる競争市場では解決できない問題であり、国が交通整理役となって道筋を示すことが求められているのです。
「プラスチックリサイクルの業界は長年の経験と知恵を持っています。ただ、時代の変化に合わせて従来の枠を超えた連携が必要です。AIを活用した共同配送など、新しい取り組みを進めてください。単独では勝負できない時代です」と細田先生は業界への期待を語りました。