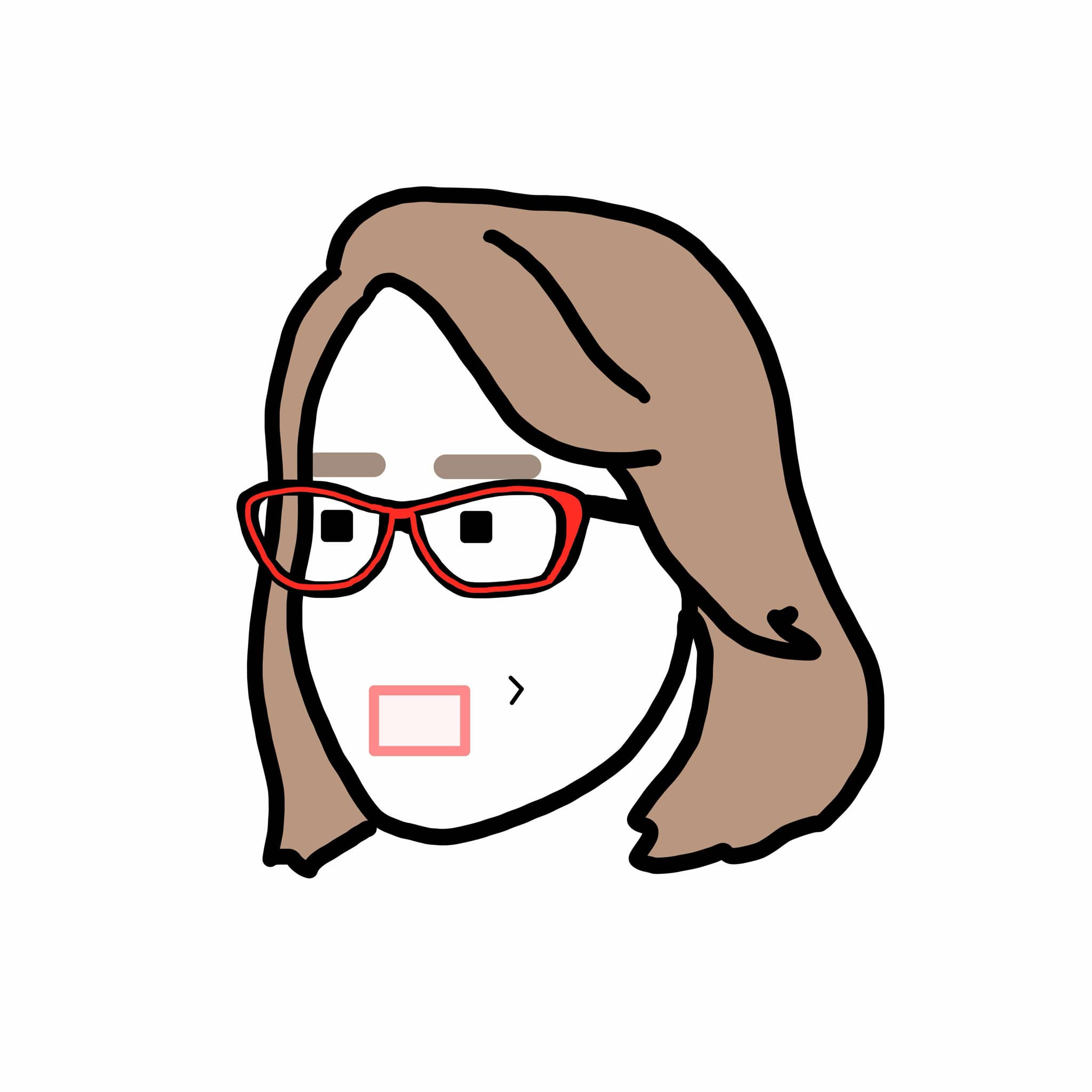今や私たちの生活に欠かせないリチウムイオン電池。しかし同時に発火や爆発のリスクも抱えており、廃棄物処理施設での火災事故が相次ぎ、社会問題になっています。この問題に取り組む早稲田大学発のスタートアップ企業が埼玉県にあります。
株式会社電知( 埼玉県本庄市)は、強みであるEV車載電池の診断技術をリチウムイオン電池にも活用し、安全な回収・リサイクルの仕組みづくりに挑戦しています。今回は同社が入居する「インキュベーション・オン・キャンパス(IOC)本庄早稲田」に、同社代表取締役CEOの向山大吉氏を訪ねました。


大学の研究をビジネスに 〜電池診断技術の事業化
—まず御社の設立の経緯を教えてください。
私は元々大学(早稲田大学)の研究者で、EV車載電池の状態評価に関する研究をしており、2020年にプログラマーである弟(CTO 向山公一氏)とこの会社を立ち上げました。私が研究者で、弟がプログラマーという組み合わせです。
当初は副業として始めようとしたのですが、大学から副業は認められず、2021年に完全に独立して本格的に動き始めました。現在は私と弟に加え、メーカー出身で電池診断の経験がある方など、少数精鋭のメンバーで事業を展開しています。

—電池診断の技術をビジネスにしようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
北京オリンピックの頃、中国で電気自動車が大量に普及し始めた時期に、電気自動車の発火事故のニュースを目にしたことがきっかけです。私たちが研究していた電池と同じものが原因で火災が起きているのを見て、こういった危険な電池を世の中から排除したいという思いが芽生えました。
日本ではEVの発火事故はあまり報道されていませんが、極めて珍しい例として、今年2月に鳥取県で日産のリーフが充電中に発火するという事故がありました。電池が起因となっているのかまだ調査中のようですが、こういった事故を防ぐためにも、電池の安全性を診断する技術が必要だと考えています。
—具体的にどのような製品に対応しているのでしょうか。
当初はEVの電池診断を主な対象としていましたが、実際には身近な電子機器の電池にも大きな需要があることがわかりました。例えば、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、電動アシスト自転車、掃除機などの家電製品に使われているリチウムイオン電池も対象としています。
特に注目しているのは、使用済みや故障した電子機器から取り出された電池です。これらは従来の方法では安全に処理することが難しく、適切な回収・リサイクルルートがありませんでした。私たちの技術を使えば、これらの電池も安全に処理し、リサイクルの道筋を作ることができます。

—今回NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の賞を受賞されたと伺いました。
はい、NEDOチャレンジ(「NEDO懸賞金活用型プログラム/リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発/NEDO Challenge, Li-ion-Battery 2025/発火を防ぎ、都市鉱山を目指せ!」)のコンテストで、当社の技術が「リチウムイオン蓄電池の発火危険性の回避・無効化装置」のテーマで1位をいただくことができました。
リチウムイオン電池の危険性を回避する画期的な装置
—受賞された「リチウムイオン蓄電池の発火危険性の回避・無効化装置」技術とはどのようなものですか。
リチウムイオン電池の処理場での破壊処理の手前で、誰でも簡単・安全に発火能力を無効化・回避することを目指した技術で、具体的には2つの要素があります。
1つ目は放電診断機で、電池の発火危険性を無効化します。ただし、これで100%評価できるわけではないので、2つ目の要素として安全に運ぶための赤く塗った箱を用意しています。放電できた電池は、従来のリチウムイオン電池回収の黄色い箱に、放電できない危険なものは赤い箱に入れ、最終的な処理場に届けるという仕組みです。
—1つ目の放電診断機の特徴について詳しく教えてください。
元々私たちは剥き出しになった電池の診断を得意としていました。その技術を応用して、経済産業省の補助金を活用しながら、家電製品に内蔵された状態の電池を評価する診断機を開発しています。
この装置は、電池から少しだけ放電させることで、電池の中身の状態を知ることができます。従来の放電方法では、海水や水に浸して放電するという方法が一般的でしたが、この方法にはいくつか問題がありました。水に浸けただけでは電池の状態が分からないこと、リチウムイオン電池と水の相性が悪いこと、そして取り出した状態の電池には適用できないことなどです。
私たちの放電診断機は、USB接続で簡単に放電できるようになっています。充電のための通常のUSB接続口を使って放電ができるようにしたことが、NEDOチャレンジで評価されたポイントの1つです。
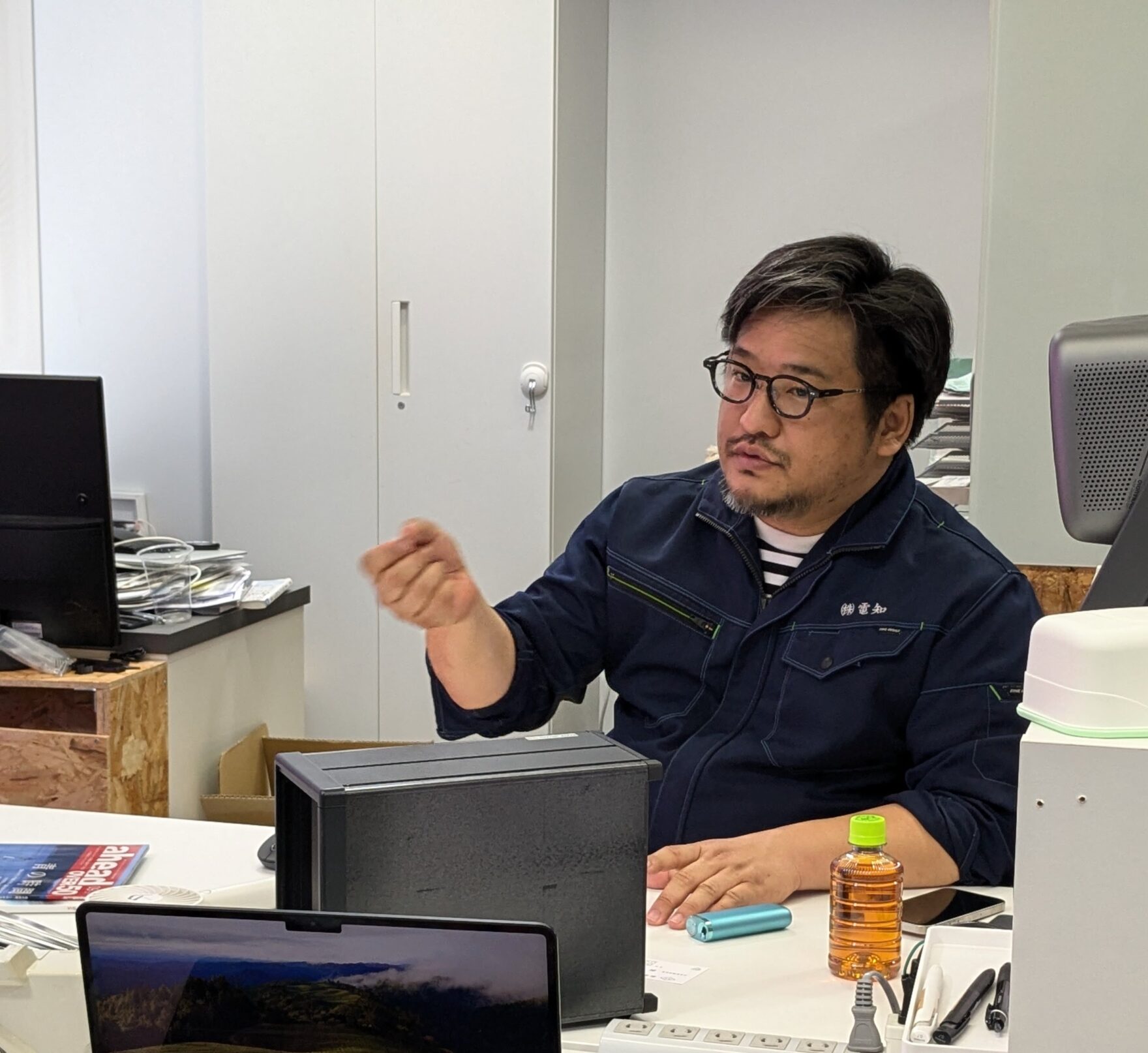
安全な回収・運搬を実現する特殊ボックス
—2つ目、放電できない電池を入れるボックスについて教えてください。
この特殊ボックスは耐熱性・耐圧性の材料でできており、内部での発熱を感知して消火機構が物理的に働くようになっています。
このボックスに入れることで、危険な状態の電池を安全に保管・運搬することができますが、同時に「危険かどうか判断できないもの」についてもこちらに入れることができます。「わからないものはとりあえずここに入れる」という位置づけのボックスにすることで、安心安全に分別・回収ができることを狙っています。
—どのような場所に設置することを想定していますか。
リチウムイオン電池の発火事故は、処理施設だけでなく、一般家庭や学校、オフィスなどさまざまな場所で起こる可能性があります。例えば、学校で使用されているタブレット端末の電池が膨張して危険な状態になる可能性も十分に考えられます。
このボックスを使えば、そういった危険な状態の電池を安全に回収し、適切に処理することができます。また、電池の状態を正確に診断することで、再利用可能な電池と廃棄すべき電池を適切に判別することもできます。これにより、リチウムイオン電池の安全性が向上するだけでなく、資源の有効活用にもつながると考えています。
循環型社会の実現に向けた展望
—今後の事業展開について教えてください。
EVの普及が進む中で、中古EVの価値を適切に評価する技術へのニーズが高まっています。車載EV診断技術に関しては、Solvvy株式会社と連携し、EV車載バッテリーに対するAI診断技術を活用した保証サービスにも取り組んでいます。
リチウムイオン電池に関しては、まずは放電診断機と安全運搬ボックスの製品化を進め、市場に投入していく予定です。同時に、自治体や廃棄物処理業者、リサイクル業者などと連携して、リチウムイオン電池の回収・リサイクルの仕組みづくりにも取り組んでいきたいと考えています。
将来的には、リチウムイオン電池のリユース・リサイクルを促進し、循環型社会の実現に貢献したいと考えています。例えば、放電した電池から回収したエネルギーを別の用途に活用する道を探るなど、電池の「ごみ」ではなく「資源」としての価値を最大限に引き出す取り組みを進めていきたいです。
—ありがとうございました。
株式会社電知
https://denchi.ai/