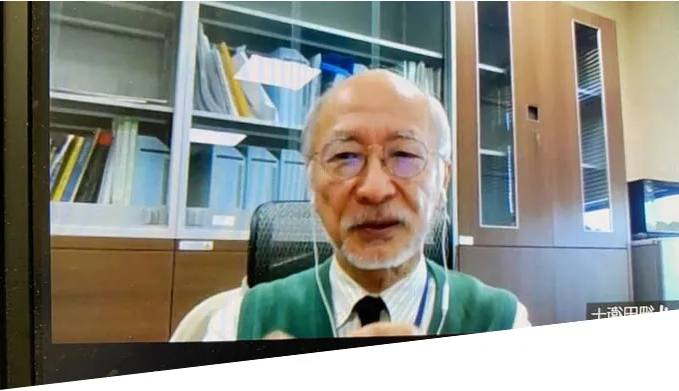長野県諏訪市を拠点に、空き家から古材や古道具を買取して販売する事業等を行うReBuilding Center JAPAN。2025年4月、これまでとは異なる古材の新たな魅力が詰まった新プロダクト「notonly(ノタンリー)」を発表し、銀座松屋で開催された「銀座・暮らしの商店街」にて販売を開始しました。
イベント会場を訪ね、共同代表の東野華南子氏にお話をうかがいました。
notonly(ノタンリー)を生み出した理由
銀座松屋8階イベントスクエアにて、2025年4月16日(水)〜21日(月)にわたり開催された「銀座・暮らしの商店街」。個性豊かな暮らしの道具を販売する店舗が集まるなか、ReBuilding Center JAPAN(以下、愛称のリビセンと表記)のスペースは入り口方向から一番奥の広いエリアに設定されていました。
リビセンは、長野県諏訪市にて古材や古道具などを扱うリユースショップ、カフェを運営するとともに、古材を使った空間設計やプロダクトの制作を手がけています。販売している商品は、周辺の解体予定の建物から直接「レスキュー(買い取り)」してきたもの。
イベント会場にも、諏訪周辺でレスキューされた食器棚や和箪笥などの大物家具から鏡、ランプ、古材から制作した一輪挿やフレームといった生活雑貨まで、大小さまざまな商品が並び、リユース品ならではの表情や味わい深さ、歴史が感じられる独自の魅力を放っています。
その一角に、今回新たに発売されたシリーズ「notonly(ノタンリー)」の紹介コーナーがありました。notonlyのプロダクトは、あえて表面を削ぎ落とした古材を使用して制作しているのが特徴で、これまでリビセンで扱ってきたものとは一線を画しています。
notonlyのブランドコンセプトが生まれた背景を、東野氏は次のように説明します。
「リビセンでは2016年の設立以来、空き家などの解体現場で古材や古道具をレスキュー(買い取り)し、それらを販売する事業を中心に活動を行ってきました。
古材には独特の表情があり、それを好きだと感じてくれる人がいる一方で、ホームプロダクトとしては、魅力がデメリットに転じてしまう部分もありました」
古材や古道具を扱う上で、これまで感じてきた課題が大きく2つあるといいます。一つは、個性が強いため家のなかで馴染みにくいこと。2つ目は、一点ものであるため卸売への対応が難しいことです。
「静かな表現を好む人にとって、古材を使用した家具や雑貨は日常使いしにくい側面があります。いいなと思っても、自宅にある他のものとは雰囲気が違い、購入するにはハードルが高いとおっしゃる方も多いです。ですからこれまでは、一定の範囲までしか広がらない現実がありました。
また、卸売については、これまでオンラインストアで行っていた時期もあるのですが、写真撮影の手間やコストが膨大で、継続することができませんでした」(東野氏)
これらを解決するために生み出したのが、新シリーズのnotonlyです。
目的は「古材と出会う人を増やす」「出会い方を変える」
あえて古材の表面を削ることで、そのまま使用するのとは異なる落ち着いた雰囲気に仕上がっているnotonlyシリーズのプロダクト。説明がなければ古材でつくられているとは気づかないほど、経年劣化や傷などの、いわゆる「古材の特徴であり魅力」される部分は見当たりません。

「デザインが気に入って買ってみたら古材だった。その結果として、環境問題や気候変動に偶然アプローチできた、アクションになった。そんな人を増やしたいと考えていくなかで、notonlyのコンセプトに行き着きました」(東野氏)
古材というキーワードに惹かれて自ら探してくれる人だけでなく、デザインや風合いなどに着目して選び古材と知る。そんな新しい古材との出会いの機会をつくりたいという思いがありました。
また、卸売への対応という意味でも、メリットがあります。レスキューする地域が同じであれば、基本的に同じ種類の木材を使用していることが多いため、ある程度統一感のあるプロダクトに仕上げることができます。細部を見れば小さな差異はありますが、「個体差がある」という範囲内に収まり、卸売が可能になるといいます。
「大量生産ともこれまでリビセンで扱ってきた一点ものとも違う、ちょうどその中間にあるのがnotonlyのプロダクトです。何十個という個数をすべて同じもので揃えることは難しいですが、ある程度表情が似た家具や雑貨で店舗やお部屋のインテリアに統一感を持たせたい、といったニーズにはお応えできるようになりました」(東野氏)
好評を博したnotonlyのプロダクト
古材の新しい魅力に光を当てたnotonlyのプロダクト。イベント(銀座・暮らしの商店街)の来客者には想像以上に好評で、特にトレイの人気が高いといいます。さらに、スツールは飲食店やオフィスの方がまとめて購入されるなど、販売は順調です。
当初イベントでは、notonlyはお披露目程度にとどめ、本格的な販売開始は5月のゴールデンウィーク明けになると考えていました。しかしイベント会場でもオンラインストアでも購入したいという声が多く、現在急ピッチで準備を進めています。
今回発表したnotonlyシリーズの第一弾のプロダクト(スツール・トレイ・フレーム)について、それぞれの特徴と魅力を下記に紹介します。
- ①スツール

3本脚が特徴的なスツールは、軽くてコンパクトな作りでスタッキングも可能。座面と脚をつなぐパーツには、目のつまった硬い木材を使用し、強度を高めているため安定感があります。
- ②トレイ
厚みのある板から削り出してつくっているため、高い強度と美しい木目を同時に実現。ラウンド(小)とオーバル(大)の2つがありますが、どちらも軽量で縁の立ち上がり部分に手をかけやすく設計されていることから、重さがかかっても配膳しやすくなっています。
- ③フレーム
建具や窓に使われていたガラスを丁寧にレスキューし、手入れをしたガラスで制作。
2枚のガラスの間に挟みこんで飾ることができるフレームです。静かな木目と透明感から生まれる包容力が魅力です。
古材の流通の仕組みを変えていきたい
notonlyシリーズ第一弾が発表されたばかりですが、今後も定期的にnotonlyのプロダクトを増やすなど、古材の可能性を広げていきたいと話す東野氏。すでにリビセンで行っている活動と組み合わせた、具体的な展望を描いています。
「リビセンは1カ月で60〜70件ほど空き家などの解体現場に出向き、家具や古材をレスキュー(買い取り)しています。とはいえ対応できるのは車で1時間圏内で、どうしても長野県内の近隣地域になってしまいます。
各地で同様に多くの古材が廃棄されていることを考えると、日本全国にリビセンのような活動をする店舗が必要です。そうした理念の元、資源のレスキューや再利用に取り組みたい人たち向けにスクール(リビセンみたいなおみせやるぞスクール)を立ち上げ、経験やノウハウを共有しています。
全国さまざまな地域から参加があり、スクール後もつながりを持っているので、今後はそうした仲間たちの地域でレスキューした古材を仕入れて、notonlyの材料として使用することを構想しています。

レスキューする地域が変われば当然使われている古材も変わるので、同じ種類のプロダクトでも違った風合いに仕上がったり、おもしろいものがつくれたりするのではないかと考えています」(東野氏)
▼リビセンみたいなおみせやるぞスクールの詳細についてはこちら
全国に仲間を増やしながら、諏訪地域でのリユースの拡大やまちづくりにも貢献してきたリビセン。来年(2026)年には10周年という節目の年を迎えることもあり、この先10年の流れも見据えています。東野氏は、「廃棄物処理の仕組みそのものに切り込んでいきたい」とその展望を語ります。
「今現在は空き家の解体に一件ごとに対応していますが、産業廃棄物業者と連携して、木材や古道具をリユースする新たなルートを確立することができれば、さらに多くの量をレスキュー(買い取り)することができます。地域の産業廃棄物業者の方も協力的なので、次の10年は新しい展開にもトライしていきたいです。
木材は、チップや燃料などにするための中間処理施設に回されてしまうことが多い資源です。でも、中間処理をするより古材として使用した方が環境負荷が少ないため、いかに木材のまま再流通量を増やす仕組みをつくっていけるかが重要になります。今後は、そうした社会の仕組みづくりにも挑戦していきたいです」(東野氏)
------
▼ReBuilding Center JAPANについてはこちら
▼notonlyシリーズについてはこちら