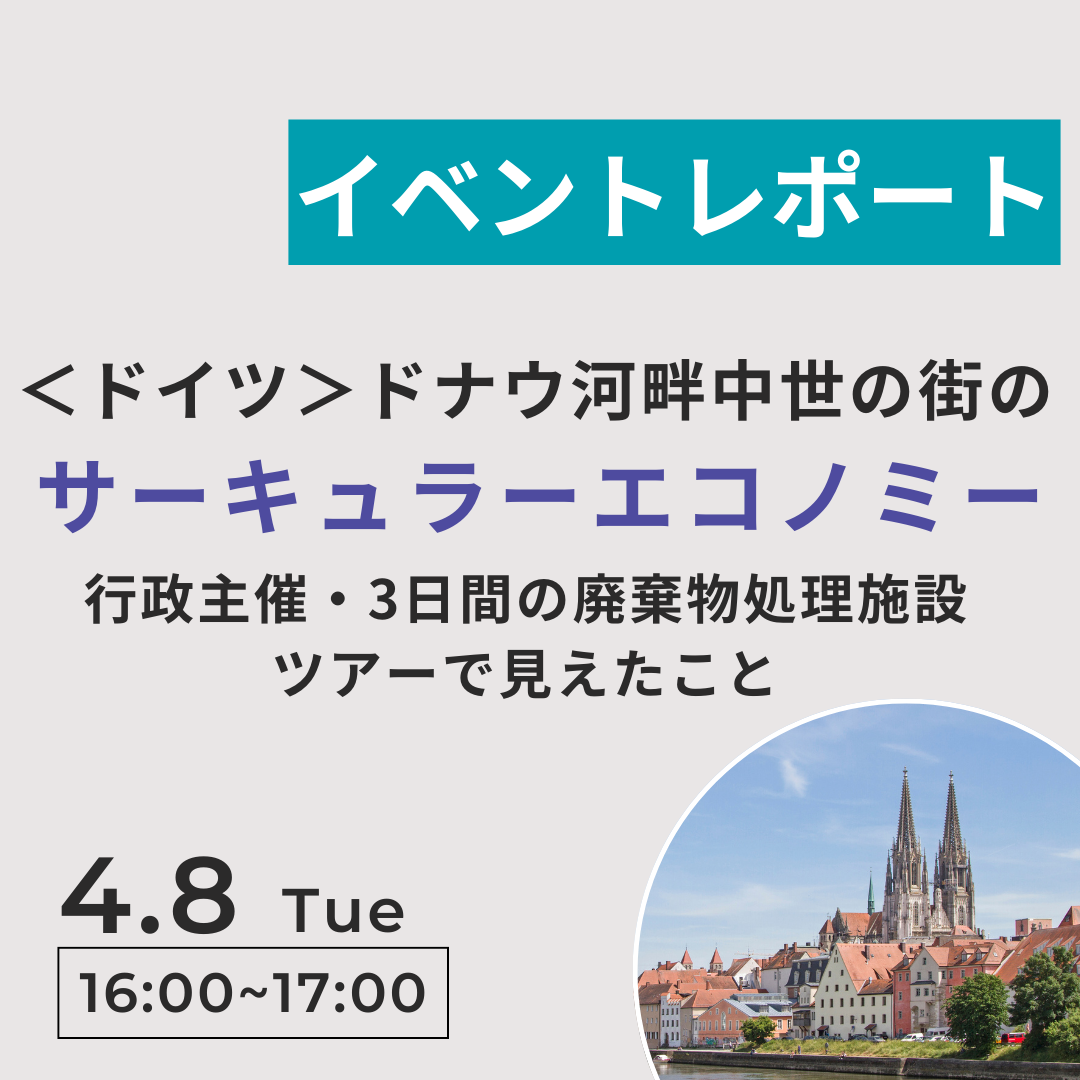4月24~26日の3日間、パリで、気候変動に対する具体策を紹介する環境サミット「ChangeNOW」が開催されました。会場は、パリの歴史的な展覧会場・美術館のグラン・パレ。世界中から1万社の企業や千人を超える投資家たちが参加し、業界内で活発な交流が行われました。

380社が展示 サーキュラー・エコノミー分野は30社超

2017年にパリで始まったChangeNOWは回を重ね、今では“世界最大の環境イベント”とうたわれるほど発展しています。今年はパリ協定(世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑える目標を掲げた国際的な枠組み)の10周年で、このイベントの重要性はさらに増したといえるでしょう。
プログラムの内容は多岐に渡りましたが、メインは会場での展示です。生物多様性、エネルギー、ファッション、食、モビリティ、海洋と水といった18のテーマに分けられ、審査で選ばれた有望な380社が出展。入り口の目の前だった「サーキュラー・エコノミー」のゾーンには、30社以上が並びました。以下、サーキュラー・エコノミーの展示者をいくつか紹介しましょう。

「FixFirst」修理業者向けのAIツール

EUでは昨年、「修理する権利」(消費者が簡単に、安く、早く修理を受けられる権利)の法が制定されました。加盟国は来夏までに国内法などを整備する必要があります。
ドイツのFixFirst社は、「修理して使い続ける」ことを広げるため、修理業者向けのソフトフェア(AIツール)を開発しました。同社のソフトフェアを使えば、修理費見積りを早く正確に行う、スペアパーツを近隣のサプライヤーで見つける、作業の優先順位などを基に修理スケジュールを最適化する、各顧客の修理記録をすべて保管して将来の修理時に役立てるといったことが可能になるといいます。
「BYSCO」何度でも循環する貝の繊維製の布

フランスのBYSCO社は、廃棄される国産のムール貝の足糸を養殖業者から回収し、不織布に加工しています。足糸とは、ムール貝から生えている天然繊維(足糸のおかげで岩や養殖用ロープなどに付着できる)。断熱性や吸音性に優れ、電車の車両や建築物、作業着などの衣類等、広い範囲で使えます。寿命を迎えた布は、再び布の材料にできます(水平リサイクル)。今のところ足糸の回収は限定的ですが、来年には工場が新設され、布の生産量を大幅に増やせるそうです。
「Mycocycle」キノコの根でごみを生分解し、建材製造

世界中で焼却または埋め立てられる建設廃棄物の量は膨大です。アメリカでは建設・解体のごみは毎年6億トンを超え、全住宅の75%を占めるという、寿命が短めのアスファルト製の屋根板もリサイクルはほぼできません。Mycocycle社は、こうした有害物質を含んだごみに菌糸体(キノコの根の構造)を増殖させて生分解し、毒性を除去することに成功しました。固まると、同社特製の耐久性のある環境に優しい建材に変わります。ごみを循環させる新しい事業です。
「RAIKU」高級ブランドも注目の美しい木製緩衝材


エストニアのRAIKU社の美しい緩衝材は、100%天然木製です。まるでリボンのようです。クリーンテクノロジーにより、使う資源を大幅に節約。紙や段ボールの製造と比較すると、材料となる木材は10分の1、水は3000分の1、エネルギーは50分の1の使用量に抑えられるそうです。化学薬品は未使用で、使用後は堆肥化できます。ルイ・ヴィトンを始め75の一流メゾンを有するLVMHグループのアクセラレータープログラムに選ばれ、それらのブランドでの導入を目指しています。
「Keep-it Technologies」消費期限をリアルタイム表示

フードロスの原因の1つは、輸送や保存の温度の変化が原因で消費・賞味期限が切れることです。ノルウェーのKeep-it Technologies社が開発したパッケージのラベルは、鮮魚や生肉などの生鮮食品の鮮度を時間と温度に応じてキャッチし、消費までの残存日数を表示します。通常の日付の刻印よりも正確で、生産から小売店での販売を経て消費者の自宅に至るまで、「早めに売ろう」「早めに食べよう」とフードロスを防ぐことにつながります。
終わりに
ChangeNOWの出展者たちを見渡すと、サーキュラー・エコノミーでもそのほかの分野でも「環境問題を解決していくヒントは無限にありそうだ」と改めて感じます。3日間で得たつながりがきっかけとなり、大きく成長する企業もあるはず。最終日は一般にも開放していて、環境対策の最前線を知るチャンスでした。ChangeNOWは、今後も社会にインパクトを与えていくことでしょう。
ChangeNOW