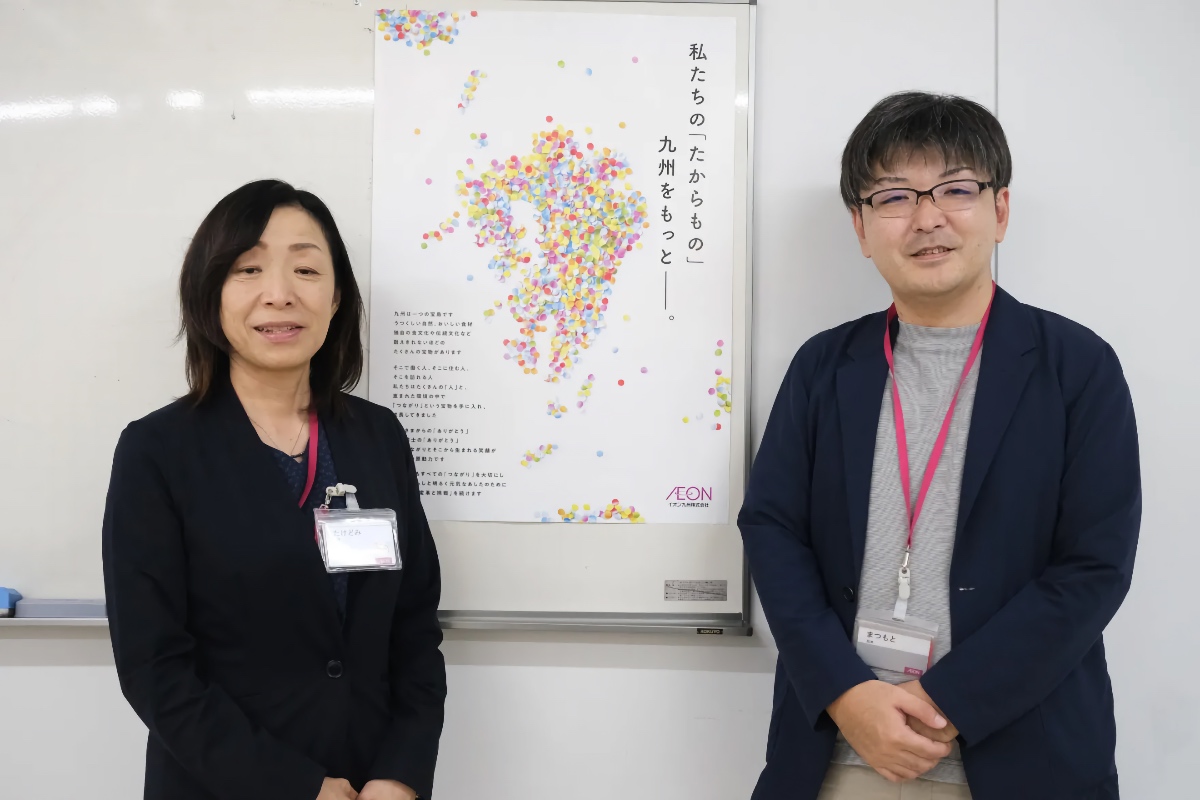渋谷と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、賑やかな街並みや最先端のファッション、そして若者文化の発信地としての姿ではないでしょうか。そんな渋谷から、いま、都市型のサーキュラーエコノミーという新しい循環の仕組みが生まれています。その中心にいるのが、「渋谷肥料」と「渋谷土産」という2つのプロジェクトを率いる坪沼敬広氏です。都市から出る廃棄物を資源として捉え直し、新たな価値を生み出す彼らの挑戦についてお話を聞きました。
渋谷の生ごみが循環の出発点に
—まず、「渋谷肥料」プロジェクトについて教えてください。
坪沼(以下略):渋谷肥料は、渋谷を「消費の終着点」から「新しい循環の出発点」にシフトできないか?という問いから始まったプロジェクトです。渋谷の事業系生ごみの量は年間30万トンにも及ぶとされています。これらを様々な手段で肥料や堆肥に変え、都会のニーズに合った商品やサービスに生かしていくことで、都市型の新たなサーキュラーエコノミーのモデルを作っています。
プロジェクトがスタートしたきっかけは、2019年9月にオープン前の渋谷スクランブルスクエアで開催されたアイデアソンイベントで、当時大きな話題になっていた渋谷ハロウィンのごみ問題と向き合うパレードの開催を提案したことでした。ただ、イベントの終了後に、生活者の皆さんの日常により浸透する取り組みが実現できないかと思い、改めて渋谷のごみ問題を調べ直してみたのです。すると全体の7割を占めるのが事業ごみで、その中でも生ごみの量がかなり多いことが分かりました。
こうした事業系の生ごみを単に捨てて燃やしてしまうのではなく、皆が欲しくなるような資源に生まれ変わらせることができたら、渋谷は”ごみが捨てられておしまい”の「消費の終着点」から、新たなモノやコトが生まれる「新しい循環の出発点」になるのではと思い、「渋谷肥料」プロジェクトを立ち上げました。
現在は、企業の社食などに機械式のコンポストを導入し、そこから生まれた肥料を屋上栽培などに用いて、企業の福利厚生やPoC(新しいアイデアや技術、サービスなどの実現可能性の検証プロセス)などと連動したプログラムを推進しています。また、渋谷の事業系生ごみの一部が茨城県で肥料化され、現地で農作物の栽培に使われていることから、収穫された農作物を再び渋谷で仕入れて商品化する「サーキュラースイーツ®」という事業にも取り組んでいます。

—「サーキュラースイーツ®」では具体的にどのようなことに取り組んでいますか?
「サーキュラースイーツ®」は、循環型の食品産業モデルで、現在は渋谷の生ごみを再利用した肥料で育てたさつま芋を使用しています。初めてリリースした『紅はるかのリ・マカロン』は、3週間の限定販売の予定が前倒しの2週間で完売するなど、大変ご好評をいただきました。

また、2023年に渋谷スクランブルスクエア内のhaishop cafeさまとコラボした「壷焼きの焼き芋とオーツミルクのアイス」は、他商品の1.5倍の価格でありながら、2倍以上の個数が売れて完売しました。さらに同年、秋田の名物アイスクリームをリニューアルした「渋ヘラ・アイス」は、ハチ公生誕100周年のアニバーサリー商品のひとつとして反響をいただきました。最近では、前述のhaishop cafeさまとの新たにコラボした「渋谷焼き芋モンブラン」と「焼き芋アイスクリーム」が好評をいただいています。



都市と地方をつなぐ新しい循環モデル
—なぜ、お菓子という形態を選んだのでしょうか?
循環の仕組みを通じて新しい商品を生み出そうと考えた時に、お洒落でクリエイティブなものと相性の良い渋谷の特性と、多くの人がワクワクするものは何かと掛け合わせた際に、老若男女を問わず好きな人が多いスイーツならば、たくさんの人たちが面白いと仰ってくださると思ったからです。
また、お菓子のマーケットは世界で30兆円以上に上るとされており、新しい技術やカルチャーとの融合で、今後さらに発展する余地を秘めています。サーキュラースイーツ®の仕組みを通じて、都市と地域に新しいつながりが生まれて、商品そのものの付加価値が高まるストーリーは、単なる廃棄物処理の枠を超えた、新たな都市と地域の連携モデルになると考えています。ちなみに我々が実施したアンケート調査では、サーキュラースイーツ®を購入した8割以上の方が、サーキュラーエコノミーに対する理解が深まったという回答が出ています。お菓子を通じて、ごみ問題や循環型社会への関心を高める効果もあるのです。
—事業を進める上での苦労したことはありますか?
新しいチャレンジをする際に強く感じることは、既存のやり方ではできないとされている制約条件をクリアする必要があるということです。例えば身近なお菓子を見た時に「どうしてこういう形になっていないのだろう?もっとこうしたほうが売れそうなのに」と思うことはないでしょうか?ただ、実際に開発に取り組んでみると、製造や保管、流通など様々な観点から制約が生じることが理解できます。しかしこれまでとは異なる視点を見出してそうした制約を超えていかないと進歩はないので、試行錯誤しながら新しいセオリーを作り続けています。苦労は絶えませんが、そうした結果、私たちならではの強みが鍛えられていきますし、私たちが為すべきことは何か?というより大きな視点を得ることにもつながります。
—今後の販売計画についてお聞かせださい。
これまで様々な飲食店様とのコラボレーションや自社商品の販売、ポップアップやイベントでの出店を通じて蓄積したデータと経験を活かして、今後はBtoC向けに商業施設への出店や卸販売、BtoB向けにホテルや空港などでの販売を進めていきたいです。さらに食品ECの市場も急速に成長していることから、ECサイトを中心としたオンライン上でのブランド展開にも力を入れていきます。
建築廃材から生まれる「建築土産」
—「渋谷土産」プロジェクトについても教えてください。
「渋谷土産」は、"わたしの好きな渋谷"の秘められた力で、渋谷をさらに魅力的な街にするには?という問いから始まったプロジェクトです。特に力を入れているのが建築家でプロジェクトメンバーの中村彩乃と取り組んでいる「建築土産」です。これは、再開発によって解体される建物の一部を素材にした、「まちや建築の『なくなる』と『うまれる』の間にある可能性を追求する」プロダクトブランドです。
現在は、昭和の名建築家・坂倉準三氏が設計した東急百貨店東横店の解体コンクリートを素材として活かした製品を作り出しており、これまでに東急株式会社様のご依頼のもと開発したマグネットツールの「kumi-tsugu」(2022年)や、東急建設株式会社様と共同開発をしたデスクオーガナイザーの「ma_desk organizer」(2024年)をリリースしました。建築土産は、単に建築廃材を素材としてアップサイクルするだけにとどまらず、徹底したリサーチと独自で開発した製法を通じて、建物の歴史や建築家の思想、その土地の文化を反映したデザインを生み出していることが特徴です。


—なぜ、建築廃材を活用しようと思ったのでしょうか?
私たちもまちづくりや地域の文化を担う存在として、その土地の建築が長く親しまれていくことが何より大切と考えています。ただ一方で、老朽化や都市計画の再整備に伴い役割を終える建築も出てくるのが現実です。そうした状況が生じた時、解体か保存かの対立にとどまらず、まちの記録と記憶を未来に受け継ぐ取り組みができないか?と考えたことがプロジェクトを始めたきっかけです。
渋谷や東京をはじめ各地で現在大規模な再開発が進んでいますが、2015年から2022年の期間に解体などで抹消された登録有形文化財の件数は189件に上り、中銀カプセルタワー(新橋)、東京海上日動ビル(丸の内)といった昭和の名建築も解体の憂き目に遭うなど、歴史的な価値を持つ建築の”記録”と”記憶”をどう未来に受け継いでいくかは社会的な問題となっています。これに対して「建築土産」は、解体せざるを得ない建築が出てきた際に、大きな建物は無くなってしまっても、今度はその建物が小さく生まれ変わって、私たちの暮らしの中で生き続けるというストーリーが展開されます。まちの”ものがたり”を”もの”として生まれ変わらせることで、今度は人と建築の新しい関わり方が動き出すのです。
未来へ向けた展望
—今後の展開についてお聞かせください。
私たちは2035年に200億円の売上を達成することを目指しています。そのために、国内はもちろん、海外市場での展開も視野に入れています。世界には「メガシティ」と称される人口1,000万人以上の大都市が既に30ヶ所以上存在しており、都市化の潮流に伴いますます増えていくことが予測されています。したがって、将来はパリやニューヨークのような世界各地の大都市圏で、周辺の地域と結びついたサーキュラーエコノミーのモデルを展開していくことが目標です。廃棄物の再資源化から、「ヒト・モノ・カネ・情報」の循環を促進する経済圏を広げていくことで、私たちの事業が人の創造性と主体的な生き方を促す動力源となることを目指しています。
—最後に、読者へのメッセージをお願いします。
元々、食は手作りするものでしたが、20世紀のリニア型経済(大量生産・大量消費・大量廃棄)の発達に伴って”工業製品としての食”が爆発的に普及しました。そうした世の中が当たり前になると「食品は捨てなきゃビジネスとして成り立たないんだよね」といったような諦めの気持ちを持っている方も多いと思います。だからこそ私たちは、21世紀の時代に循環型の食産業モデルを確立していきたいです。
スイーツというアウトプット自体はシンプルなものですが、私たちの取り組みを見て、「自分たちも何かできるかもしれない」と思っていただける方が増えたら嬉しいです。一人一人の小さな行動が、社会に大きな変化を生み出す原動力になると信じています。
ーありがとうございました。