ブルー水素とは、化石燃料を原料として生産される水素のうち、二酸化炭素(CO2)を回収・貯留することで排出を抑えた水素のことを指します。
水素は、再生可能エネルギーと並んで脱炭素社会の実現に向けた重要なエネルギーキャリアとされています。その中で、ブルー水素は、天然ガスや石炭などの化石燃料から水素を製造する際に発生するCO2を、CCS(Carbon Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)技術やCCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage:二酸化炭素回収・有効利用・貯留)技術を用いて大気中に放出せずに処理することで、従来のグレー水素(CO2を回収せずに排出する水素)と比較して環境負荷を低減する手法です。これにより、ブルー水素は水素の大量生産を実現しつつ、カーボンニュートラルを目指すための中間的な選択肢として位置付けられています。
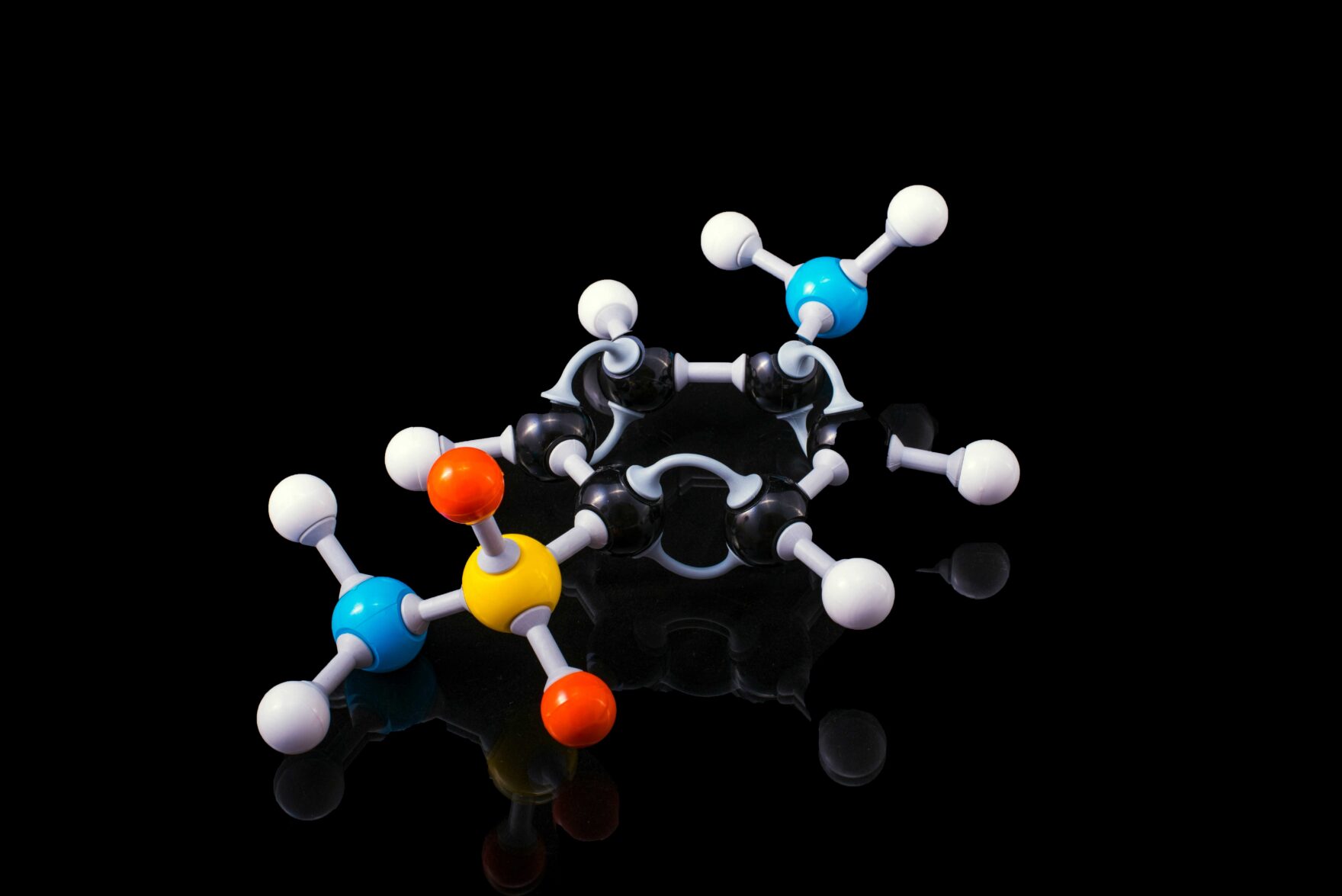
ブルー水素の目的は、従来の化石燃料に依存したエネルギー供給を維持しつつ、CO2排出を抑制し、持続可能な水素社会の基盤を築くことにあります。
水素の生産方法には、ブルー水素のほかに、グリーン水素(再生可能エネルギーを利用した水電解により生成される水素)やグレー水素などがあります。グリーン水素は理想的な選択肢ではありますが、現時点ではコストや技術的課題が多く、大規模な普及には時間がかかると考えられています。そのため、短中期的な脱炭素戦略の一環として、ブルー水素が注目されています。特に、エネルギー資源が豊富な国では、天然ガス由来のブルー水素生産が進められており、CO2の回収・貯留技術の発展とともに、その導入が加速しています。
また、ブルー水素の導入は、既存のエネルギーインフラを活用できる点も大きなメリットです。水素を燃料とする発電や産業利用、燃料電池車(FCV)などの分野で、ブルー水素を活用することで、化石燃料の使用量を削減しながら、段階的にグリーン水素への移行を進めることが可能になります。
ブルー水素は、カーボンニュートラル社会の実現に向けた移行期の選択肢として、エネルギーシステムの変革を促進する役割を果たします。
ただし、ブルー水素にはいくつかの課題も存在します。まず、CO2の回収率が100%ではないため、完全に排出ゼロの水素生産とは言えません。また、CCSやCCUS技術の普及にはコストがかかり、貯留場所の確保や環境負荷の評価なども重要な課題です。さらに、一部では、化石燃料の利用を継続すること自体が持続可能な解決策ではないとの批判もあります。
そのため、ブルー水素の導入は、グリーン水素への移行を見据えた「過渡的な技術」として捉えられるべきであり、長期的には再生可能エネルギーを活用した水素生産が主流となることが期待されています。今後、CO2回収技術のさらなる進展やコスト削減が進めば、ブルー水素の活用範囲も広がり、より持続可能なエネルギーシステムの構築に寄与する可能性が高まります。
